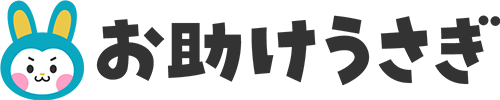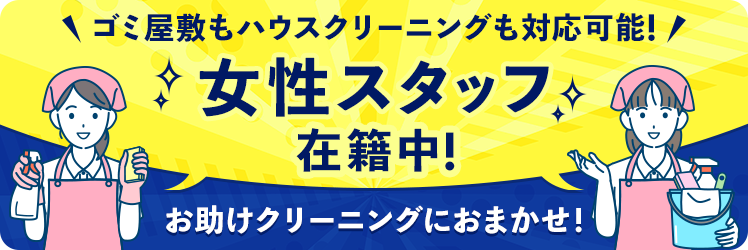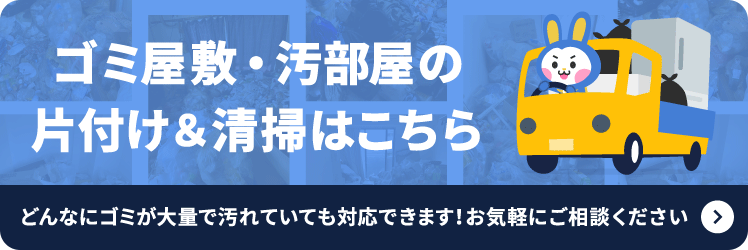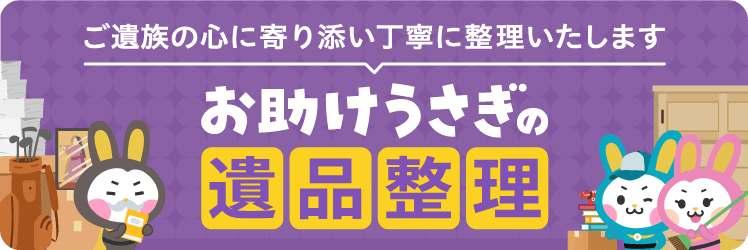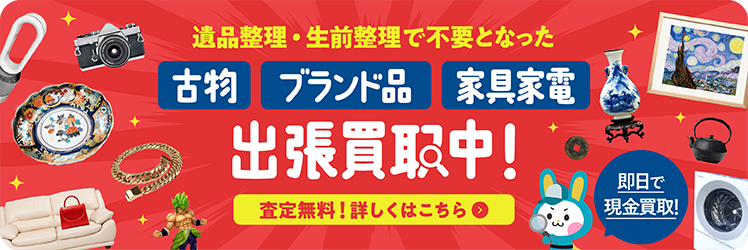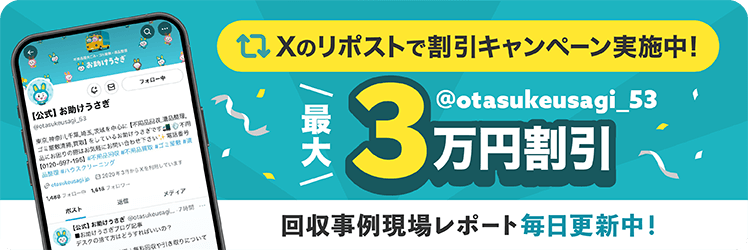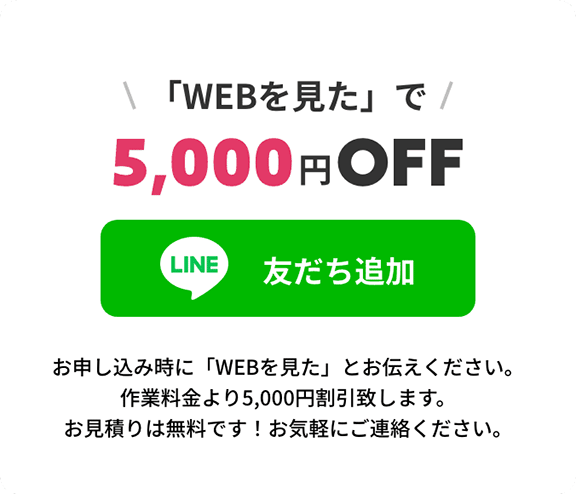土の捨て方7選|無料回収や引き取りについて詳しく解説
不用品別の処分方法「簡単にストーブを処分する方法はある?」
「冬前に買い替えを検討しているけど古いストーブの処分が面倒だな…」
「灯油が残ったまま捨ててもいいのかな?」
ストーブは寒い冬の季節に大活躍する暖房器具です。暖房といえばエアコンやヒーター、電気カーペット、コタツなど様々なものが販売されていますが、その中でもストーブは見劣りすることなく昔から多くの人に愛されてきた製品です。
そんなストーブの処分に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。特にサイズの大きいストーブであれば運ぶのも一苦労であり、処分せずに物置にしまい込んでしまっているということも珍しくありません。
冬本番になる前に買い替えようと思っていたけれど、捨てるのが億劫で結局古いストーブを使い続けているという人もいるのではないでしょうか。古いストーブの処分ができなければ新しいストーブの購入にも進みづらいものです。
そこで本記事では、ストーブの捨て方・処分方法について詳しくご紹介させていただきます。処分に掛かる費用や注意したいポイントなど詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。
この記事を読むと以下のことが分かります。
・ストーブの正しい処分方法
・処分費用や注意点
・ストーブに残った灯油の扱いについて
【ストーブと一緒に、ご自宅の不用品もまとめてスッキリしませんか?】
\夏の5000円OFFキャンペーン実施中!/
詳細はバナーをタップしてお問合せください↓↓
ストーブについて
ストーブとは、冬場に使用をする暖房器具の一種であり、一般家庭から事業所、公共施設や商業施設に至るまで非常に多くの場所、人々に利用されています。
昨今の一般的なストーブはそれほど大きさもなく移動も容易なものでもあるため、電源コードさえ確保できれば様々な場所で利用できる利便性の高さがあります。
最近では電気代高騰の影響も受け、エアコンの使用は控えて電池で動くストーブやガスを利用するストーブの利用に切り替えたという人もいるのではないでしょうか。
ストーブと聞くと少し古いイメージにも思えるかもしれませんが、今もなお私たちの生活を支えている立派な家電であることが見受けられます。
種類や使用の違い
ストーブには大きく分けて4つの種類があります。
種類によって特長が大きく異なり、使用環境にも大きく影響してくることとなるため、自分にとってどのストーブが最適なのかはしっかり吟味をしたうえで選ばなければいけません。
石油ストーブ(灯油ストーブ)
燃料に灯油を利用して熱を出すタイプです。
電気を使用しないので屋外でも利用することが可能となっています。キャンプや釣りなどアウトドアを楽しむ際に利用されたり、災害時に活用をされることもあります。室内であってもコンセントの位置を気にせず気軽に暖を取ることができる優れものです。
ただし、利用には細心の注意が必要です。燃料として使用をする灯油は危険物の一種であり、使用方法を誤ってしまうと火災や爆発などの原因となってしまいます。
また、電気代が掛からない代わりに、灯油を購入するランニングコストは掛かってしまうこととなります。灯油は電気代以上に価格の変動が激しく、時勢によって急激に高騰する可能性があるといったことも理解しておかねばいけません。
ただし、灯油を使用することによる独特の匂いがあることや燃料となる灯油の保管場所を用意する必要があるなど、使用には多少の手間が掛かる部分もあります。
ガスストーブ
燃料にガスを利用して熱を出すタイプです。
ガス栓を供給元として利用をするタイプはガスの残量を気にする必要がないため人気がありますが、設置場所が限定されてしまうことには注意しましょう。
別タイプとしてカセットボンベからガスの共有を行えるものもあり、こちらはボンベさえ準備をしておけば屋内外問わずどこでも使用可能となっています。
灯油のように独特な匂いを発することがないため、匂いに敏感な人でも気軽に利用することができます。ただし、万が一ガス漏れが発生した時のことも考えて定期的に換気を行う習慣をつけることをおすすめします。
また、コスト面でいうとガス代が掛かることとなるため光熱費を気にする必要が出てきます。使用するガスの種類が都市ガスかプロパンガスかなどによっても価格が左右されるため、ご自身の住環境を鑑みたうえで利用を検討することになるでしょう。
電気ストーブ
上記の2種類とは異なり、こちらは電気を利用するストーブとなります。ストーブという名称ではあるものの、機能としてはヒーターと同種となり、ハロゲンヒーターやカーボンヒーターと呼ばれることもあります。
灯油やガスを使用しないので匂いや空気環境を気にする必要はありません。ただし、電気は必須となるためコンセントの位置を気にして設置しなければいけないといった点には気を付けましょう。
また、比較的コンパクトなデザインのものが多く、部屋全体を暖めるというよりは室内の一区画だけを暖めることに優れています。足先だけ暖めたい、脱衣所を使用している時だけ使用したいなど、1つのポイントに絞って利用することをおすすめします。
ピンポイントでの使用が適されているからこそ、即暖性に非常に優れています。起動をして数秒で熱が放出される優れものです。プラスアルファの機能として人感センサー付きや加湿機能付きも人気となっています。
薪ストーブ
燃料に薪を使用する昔ながらのタイプです。設置には専用の設備が必要なため日本の一般家庭で使用をしている人は多くはありませんが、こちらも立派なストーブの一種です。
薪を実際に燃やして暖を取るという仕組みとなっており、火がストーブの外側に出てしまわないよう鉄や鋼製の箱でしっかりと密閉されています。燃やしたことによって発生した煙やガスについても室内に漏れ出してしまわないよう専用の煙突を取り付けて屋外に排出するといった非常に大がかりな設備で利用をすることとなります。
薪ストーブから発生する熱量は凄まじいもので、その暖かさは石油ストーブの2倍以上といわれています。一個人で利用ができる暖房器具としては最大級に暖かいといっても過言ではありません。
しかし、先述の通り大規模な設備が必要であることと、大量の薪を日常的に用意しなければいけないということから、流通量としては他のストーブに劣るといえるでしょう。
本記事では一般的に流通している石油・ガス・電気ストーブの捨て方・処分方法についてご紹介させていただきます。
価格や相場
ストーブの購入価格は種類によって大きく異なります。
| 種類 | 価格相場 |
| 石油ストーブ | 15,000~30,000円程度 |
| ガスストーブ | 10,000~50,000円程度 |
| 電気ストーブ | 4,000~15,000程度 |
全体を通して暖房器具としての価格は高めといえるでしょう。特に石油ストーブやガスストーブの価格は高めといえます。燃料を入れて保管しておくという関係上サイズが一定以上あること、また使用する燃料に危険性が伴うものであるため安全対策機能が備わっていることも関係しています。
ただし、ガスストーブの場合はカセットボンベ式を選ぶことで小型で比較的安価なものを購入することも可能です。
電気ストーブについては手の届きやすい価格で販売されています。コンパクトであること、電気さえあれば誰でも簡単に利用できるという特質があるため、流通数も多く、価格もそこまで高くはありません。
しかし、誰にでも利用できる製品だからこそデザイン性も豊富であり、機能も充実しています。色や形、性能にこだわりたいという場合は1万円前後は掛かるとみておいた方が良いでしょう。
寿命と耐用年数
ストーブの耐用年数は6年、寿命は約8年とされています。
壊れなければ8年以上使い続けることも可能ではありますが、ストーブ製造メーカーによる部品保有期間は約6年とされており、製造から6年以上が経過したストーブは修理ができないこととなります。
ストーブを主要な暖房器具として使用していた場合、冬場の寒い時期に突然壊れてしまって修理もできず、急遽新しいストーブを買うためにバタバタしてしまうという事態に陥りかねません。
そのため、使用を始めてから6年目が近づいてきた時点で、処分や買い替えを検討し始めた方が得策といえるでしょう。また、耐用年数関係なく、使用する前と後で自己点検を行っておくことをおすすめします。
ストーブは絶対に安全な製品だというわけではありません。使用方法を誤ったり、管理が不十分であったりすると火災などの被害が出てしまう危険性が十分にあります。実際にストーブの長期間の使用、点検不足による事故が起こり、ニュースで注意喚起されたこともあります。
参照:読売新聞オンライン 石油暖房機器には寿命、8年で「点検・交換を」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210419-OYT1T50091/
ストーブは非常に便利は暖房器具ですが、使用する際は十分に気を付けましょう。
何ゴミで捨てられるのか?
ストーブは「粗大ゴミ」として捨てることができます。
一般的に、大きさが30cm以上あるものは大型のゴミとして見なされ、多くの自治体では粗大ゴミとして分類されます。多くのストーブもその規定に当てはまる場合には粗大ゴミとなります。
しかし、逆をいえば30cm未満のストーブであれば普通ゴミとして捨てることが可能です。石油ストーブやガスストーブは大型であるため難しいところですが、電気ストーブであれば小型のものも多く販売されており、30cm未満であることも珍しくありません。
普通ゴミとして捨てる場合は「不燃ゴミ」「小型家電」などに分別されることも多いですが、自治体により分別方法が異なるため必ず確認をしてから処分しましょう。
また、大きさに関わらず自治体ごとにストーブ製品については粗大ゴミとして品目指定されている場合も多いため、あらかじめ確認をしておきましょう。
中身は必ず抜いた状態で捨てましょう
石油ストーブやガスストーブの場合、中に灯油が入っていたりカセットボンベがセットされたままになっていることもあるかと思います。これらはストーブとは別に処分をしなければいけません。
ストーブを捨てる前に必ず中身を確認し、燃料が残ったままであれば完全に抜き取り、空になった状態で捨ててください。また、乾電池を使用するストーブも中にはあります。乾電池に関してもストーブとは別にして捨てなければいけません。
あくまでも「ストーブのみを処分する」のであって、ストーブ本体とは別物とみなされる燃料や電池については一緒に捨ててはいけません。
壊れてしまって動かなくなったストーブの中に燃料が入ったままというような場合には、多少手間は掛かりますが、しっかりと燃料を抜き取ってから処分に出すということを徹底しましょう。
ストーブの処分方法9選

ここからはストーブの処分方法を9つご紹介します。
① 普通ゴミとして処分する
② 粗大ゴミとして処分する
③ 家電量販店のリサイクル回収で処分する
④ 買い替え時に処分する
⑤ リサイクルショップで売却する
⑥ フリマアプリやネットオークションで売却する
⑦ 寄付をする
⑧ 知人・友人に譲る
⑨ 不用品回収を利用して処分する
それぞれ詳しくみていきましょう。
① 普通ゴミとして処分する
小型の電気ストーブであれば普通ゴミとして捨てることが可能な場合があります。こちらは自治体の規定により異なってくるでしょう。
目安としてはサイズが30cm未満であるかどうかとなります。電気ストーブは使用ポイントを絞って限定的な暖め用として15~25cm程度の小型タイプも多く販売されているため、そういった小さなストーブについてはゴミ袋に入れて一般ゴミ収集で捨てることができます。
分別方法としては不燃ゴミに該当することが一般的です。普段から不燃ゴミを捨てている際と同じ方法で捨てることができるため手軽ではありますが、ゴミ袋に入れる場合は、事前に使用を完全に終えている状態でしっかりと準備して捨てるようにしましょう。
また、自治体によっては「小型家電」として分別され収集を行っていることもあります。不燃ゴミではなく小型の電化製品は別けて収集を行っているという自治体も多いでしょう。
一部自治体を例にして、ストーブの分別方法について確認してみましょう。
| 自治体 | 分別方法 |
| 東京都渋谷区 | 不燃ゴミ |
| 東京都西東京市 | 小型家電 |
| 埼玉県朝霞市 | 小型家電 |
| 埼玉県春日部市 | 小型家電 |
| 千葉県松戸市 | 不燃ゴミ |
注意点として、自治体によっては「ストーブ品目」をサイズに関係なく粗大ゴミとして処分しなければならない場合があることです。また、石油ストーブ・ガスストーブに関しては基本的に粗大ゴミ扱いです。
普通ゴミとして捨てられるのであれば手間も費用も掛からず楽ではありますが、捨てられるストーブには限りがあるということを覚えておきましょう。
② 粗大ゴミとして処分する
先ほど普通ゴミで捨てられるストーブがあるとご紹介しましたが、一般的にはストーブは自治体の回収する粗大ゴミとして捨てることがメジャーとなっています。
サイズも大きく重量もあるため、普通のゴミ捨てのようにゴミ袋に入れてゴミ収集に出しておくといった捨て方ができないことを認識しておきましょう。
粗大ゴミとしてストーブを捨てる際は、まず初めに中身の確認を行ってください。灯油が入っている場合は空にする必要があります。カセットボンベがセットされている場合は取り外してください。電池を使用している場合も取り外しましょう。
中身の確認が終わったら粗大ゴミとして回収してほしい旨を自治体側に依頼・申し込みをしてください。基本的に粗大ゴミの処分は事前申し込み制となっています。
混雑時は申し込みをしてから1ヶ月以上待たなければいけないこともあるため、処分をしたいと思った段階で早々に申し込みを済ませておいてください。特にストーブの処分を検討するであろう冬場は大掃除シーズンでもあり、年末年始は粗大ゴミ回収が非常に混雑するため注意してください。
また、回収は有料であることが多いため、申し込みの際に費用の確認も忘れずに行いましょう。以下は一部自治体の例です。
| 自治体 | 回収費用 |
| 東京都中央区 | 400円 ※ヒーターは600円 |
| 東京都新宿区 | 消費電力40w以下もしくはタンク容量5L以下…400円 消費電力40w以上もしくはタンク容量5L以上…900円 |
| 東京都三鷹市 | 200円 |
| 神奈川県横浜市 | 200円 |
| 神奈川県相模原市 | 400円 |
| 埼玉県越谷市 | 一辺が50cm以上120cm未満…400円 一辺が120cm以上180cm未満…800円 一辺が180cm以上…1,200円 |
| 埼玉県戸田市 | 400円 |
| 埼玉県所沢市 | 500円 |
| 千葉県千葉市 | 390円 |
| 千葉県浦安市 | 520円 |
自治体によってはストーブの種類や容量によって費用が変わることもあるため注意が必要ですが、比較的安価で捨てられるため経済的負担がそこまで掛かるというわけでもありません。
申し込み時期と費用確認に注意を払い、処分を進めましょう。
ストーブに燃料や電池が入ったままだと、せっかく申し込みをしても回収してもらえません。灯油や電池はそれぞれ別の方法で処分をする必要がありますが、自治体によって扱いが異なるため灯油や電池の分別方法についても確認しておくと安心です。
③ 家電量販店のリサイクル回収で処分する
家電量販店では、不要な電化製品のリサイクル回収というものを行っています。利用は有料とはなりますが、回収された家電はゴミとして廃棄されるのではなくリサイクルされることとなるため、地球環境に優しい処分方法といえます。
どちらの店舗でも行っているサービスではありませんが、大手家電量販店であれば大抵行っています。店舗にてストーブ製品を販売している状況であれば、多くの場合は対応が可能でしょう。
以下はストーブをリサイクル回収してくれる店舗の一例です。
| 店舗名 | 回収費用 |
| ケーズデンキ | 2,200円 ※石油ストーブに限る |
| ヨドバシカメラ | 2,200円 ※石油ストーブに限る |
| ヤマダデンキ | 1,650円~ ※電気ストーブに限る |
| ビックカメラ | 1,958円~ ※電気ストーブに限る |
表を見て分かる通り、店舗ごとに費用が異なること、対象品目が異なることに気を付けましょう。
また、石油ストーブの回収を依頼する際は基本的に灯油を抜いておかなければいけません。家電量販店がリサイクルできるものはストーブ本体であって、中の燃料については対象外となっていることは覚えておきましょう。
④ 買い替え時に処分する
秋の終わりから冬にかけてストーブの買い替えを検討するという人は少なくありません。そんな時に利用をしたいのが買い替え時に不要なストーブを無料回収してもらうという方法です。
このサービスはホームセンターでも行っていることが多く、お近くにストーブを販売しているホームセンターがあるようなら店舗に相談をしてみましょう。以下は引き取りサービスを実施している店舗の一例です。
| 店舗名 | 回収条件 |
| カインズ | ・店舗持ち込み必須 ・新しいストーブ購入時の納品書や領収書が必要 |
| 島忠ホームズ | ・実店舗での買い替えのみ対象 ・灯油は抜き取っておく必要あり |
| コーナン | ・引き取りサービスのPOPが貼ってある店舗のみ利用可 ・コーナンPROでも引き取り可 |
| バロー | ・石油ストーブ、ファンヒーターのみ引き取り可 ・店舗持ち込み必須 |
| ビバホーム | ・店舗持ち込み必須 ・灯油は抜き取っておく必要あり |
前提として、このサービスはストーブの買い替えが必要となります。買い替えるストーブは同種類かつ同数の場合に限るため、電気ストーブを購入して石油ストーブを引き取ってもらうといったことはできないため注意してください。
また、店舗への持ち込みは必要なのか、灯油の抜き取りが必要なのかは必ず確認をしておきましょう。
同じように買い替えに伴う回収をしてもらえるイメージがある家電量販店の場合には、「購入+処分」となる場合が多いため、そちらは無料で回収してもらうことにはならないことが多いです。
ホームセンターでの引き取り処分は条件を満たさなければならない場合が多いです。そのほとんどが、「購入時のレシートの提示」「同様の製品の購入」となります。そのため、サービスを利用できないことが多かったり、処分だけを進めることができないものとなってきます。
⑤ リサイクルショップで売却する
まだ壊れておらず比較的綺麗な状態のストーブであればリサイクルショップで売却することが可能です。
ストーブのような季節性の高い家電は、時期にあわせてリサイクルショップ側が買取強化を行っている場合が多く、季節を考慮して売りに出すことで高値での買い取りにも期待ができます。
狙い目は冬前の9~11月頃となります。冬本番の12月や1月でも売ることは可能ですが、リサイクルショップ側の視点でみると、買い取った後に点検や清掃をし、売値を決め、商品を並べて初めて売ることができるようになります。そういった工程を考えると、冬本番の需要が最も高まる前の時期に買取強化を行っていることが多いです。
季節・時期を狙うことも大切ですが、より高値での買い取りを狙う場合は、汚れの状態や付属品の有無にも気を付けましょう。給油口の蓋が取れてしまってはいないか?持ち手が外れてしまってはいないか?ストーブが購入時と同じ状態であることが大切です。取扱説明書もセットにしておくと尚良いでしょう。
リサイクルショップでの売却は、売るまでに多少の手間が掛かってはしまいますが、不要なストーブをお金に換えるメリットが大きい方法ですので、ぜひ検討してみてください。
リサイクル店に売却する場合には、買い取ってもらいたい商品をお店に持ちこむ必要があります。そのため、買い取ってもらえずに持ち帰ることがないように、事前にお店に電話などで確認しておくなど準備をしておくとやり取りもスムーズです。
⑥ フリマアプリやネットオークションで売却する
買取でいうと、フリマアプリやネットオークションを利用して個人的に売却をすることも可能です。こちらの方法は業者相手ではないため比較的自分の希望する価格で売ることが可能となります。
特に、どんなご家庭でも使用がしやすい小型電気ストーブや、アウトドアで活用できる携帯型石油ストーブは人気商品です。電気ストーブはサイズもコンパクトであり機能も豊富なため、一人暮らしで大型のストーブを買うほどではないと悩んでいる人に需要があります。携帯型石油ストーブは冬場のキャンプに大活躍するため一定の需要が見込めます。
大型のストーブも売ることができないわけではありませんが不向きかもしれません。しかし、フリマアプリやネットオークションでは、売れた後に相手側に商品を郵送する必要があります。そのため、大型ストーブとなると郵送料が掛かること、梱包が手間であることがネックとなってしまいます。
これらは、あくまでも各商品ごとに人気があるかどうかの話であるため、どんなストーブであっても需要が見込めることは確かです。不要なストーブがあれば需要が高まる冬場前や冬本番時に出品をして購入されることに期待しましょう。
⑦ 寄付をする
季節家電は支援品として寄付をすることが可能です。ストーブも対象となっています。
暖房器具は寒さを凌ぐうえで非常に重要なアイテムであり、場所によっては絶対に手放せないということもあるでしょう。しかし、国内外問わず誰しもがストーブを所有できているわけではありません。
発展途上国であったり、国内の被災地や児童養護施設などでは暖房器具の支援を待っている人が大勢います。人でなくとも、犬や猫の保護施設で支援を望んでいることもあります。
不要なストーブをゴミとして捨ててしまわず、ぜひ寄付というかたちで手放すことも検討してみてください。
支援先は自治体の情報冊子で確認をするか、インターネットで探すことが可能です。支援先によって寄付の方法が異なるため、段ボールの用意は必要なのか、配送料は掛かるのかなど、準備するものと費用面を確認しておきましょう。
寄付により製品を送る場合は郵送する必ず必要があります。多くの場合、寄付先の団体へは実費で送る必要があるため、あらかじめその点は頭に入れておきましょう。
⑧ 知人・友人に譲る
壊れていないストーブの処分方法として売却や寄付を挙げさせていただきましたが、これらは多少なりとも手間が掛かることは事実です。そこで検討をしたいのが譲渡という方法です。
友人や知人、家族など身の周りでストーブの購入を検討している人はいないでしょうか。もしストーブを探している人がいれば声を掛けてみましょう。中古ではあるものの無料で譲ってくれるとなれば相手にとってもメリットは大きく、欲しいと言ってくれる人も多いです。
ただし、譲る際は相手の条件をしっかりと聞いておきましょう。石油ストーブは灯油の準備・管理が必要であり、誰でも簡単に利用できるものではありません。ガスストーブも同様です。電気ストーブであれば需要も見込めますが、サイズやデザインが好みではない場合は断られてしまうこともあるでしょう。
無理に押し付けてしまうようなことがあると今後の関係にも影響が出てきてしまうため、相手の状況を考えつつ、まずは簡単に探してみるというかたちで話を持ち掛けることが大切です。
⑨ 不用品回収を利用して処分する
最後に不用品回収業者に依頼をしてストーブを回収してもらう方法をご紹介します。
不用品回収業者は、その名の通り不要な物を回収する専門の業者です。家で使わなくなった家具、家電、日用品、ゴミにいたるまで何でも回収してもらえます。
ストーブももちろん回収可能です。石油ストーブであってもガスストーブ、電気ストーブであっても回収してもらえます。燃料を取り出さずとも回収してもらえることもあるため、ストーブの処分方法としては1番手軽といって良いでしょう。
回収日時は依頼者側の都合に合わせてくれる点も大きなメリットです。年末の大掃除シーズンであっても駆けつけてくれます。即日回収してくれる場合もあり、自治体のゴミ回収のように取集日を待つ必要もありません。
その代わりとして、ある程度の費用が掛かることは理解しておきましょう。便利であるからこそ、それなりの料金が発生します。価格は業者により異なるため一概にはいえませんが、4,000円~が相場です。
不用品回収業者に依頼をする際、突然回収作業に入るわけではなく、まずは見積もり出しをしてもらえるため、見積もり額を確認して納得がいくようであれば正式に依頼を進めましょう。
処分費用の相場・メリット・デメリット

ここまで、ストーブを処分する方法について解説してきましたが、処分方法ごとに費用も特徴も異なることがお分かりいただけたかと思います。
改めて処分方法ごとに掛かる費用と、メリットやデメリットを比較してみましょう。
| 処分方法 | 費用相場 |
| 普通ゴミ | 無料 |
| 粗大ゴミ | 200~1,500円 |
| 家電量販店 | 1,500~2,500円 |
| 買い替え | 無料(新たな購入が必要) |
| リサイクルショップ | 無料 |
| フリマアプリ ネットオークション | 無料(配送料が掛かる場合あり) |
| 寄付 | 無料(配送料が掛かる場合あり) |
| 譲渡する | 無料(配送料が掛かる場合あり) |
| 不用品回収 | 4,000円~ |
メリット・デメリット
| 処分方法 | メリット | デメリット |
| 普通ゴミ | ・手軽に捨てられる ・他のゴミと一緒に捨てられる | ・小型の電気ストーブに限る ・分別方法の調査が必要 |
| 粗大ゴミ | ・ストーブの種類は限定されない ・大型のものでも処分可能 | ・多少費用が掛かる ・灯油や電池は抜く必要がある |
| 家電量販店 | ・リサイクルに貢献できる ・大型のものでも処分可能 | ・費用が掛かる ・ストーブの種類が限定される |
| 買い替え | ・購入と同時に処分可能 ・無料で捨てられる | ・新しいストーブの購入が必須 ・店舗により条件が異なる |
| リサイクルショップ | ・お金に換えられる ・時期を選べば高額買取可能 | ・壊れているものは売れない ・付属品の準備や掃除が必要 |
| フリマアプリ ネットオークション | ・お金に換えられる ・納得のいく価格で売却可能 | ・壊れているものは売れない ・製品によって需要が異なる |
| 寄付 | ・社会貢献活動になる ・喜んでもらえる | ・支援先を探す必要がある ・寄付方法の確認が必要 |
| 譲渡する | ・気軽に手放せる ・喜んでもらえる | ・相手の好みや需要の確認が必要 ・相手が見つからないこともある |
| 不用品回収 | ・中身を気にする必要がない ・ストーブの種類は限定されない ・回収日時が決められる ・ストーブ以外も処分できる | ・費用が掛かる |
壊れていないストーブであれば売ったり、寄付をしたり、譲ったりと、誰かにまた使ってもらえるかたちで処分することができます。
壊れている・故障しているストーブの場合は自治体のゴミに出したり、買い替えやリサイクルといった方法を検討することができますが、条件によっては処分できるストーブの種類が限定されてしまうこともあります。
ゴミとして廃棄したい、今すぐにでも処分をしたいと思っている、そんな場合は不用品回収サービスの利用が便利です。ただし、費用は掛かってしまいます。
どの方法を選ぶ場合にも、良い面・悪い面があるため、ご自身にとってメリットの大きい方法を選択することが大切です。
ストーブの処分を見極める基準4つ
耐用年数に満たないストーブでも、劣化状況によっては処分が推奨される場合もあります。
少しでもストーブに異変を感じたら、速やかに使用を中止し、点検を行ってください。そのまま使用を続けていると発火や一酸化炭素中毒になってしまう危険性があります。
また、その異変が耐用年数以内に発覚したものであれば処分をせずとも修理をするというかたちで使い続けることが可能です。
ここでは、処分や修理を検討すべき事象についてご紹介します。
エラーが何度も出る
使い方に何の問題もないけれど、ストーブがエラーを発し続けているという場合は注意してください。
まずは使用を止め、取扱説明書を見てエラーの解消ができるかどうか確認をしてみましょう。フィルターやストーブ内部の詰まりなどであれば対象部品を掃除することでエラーが解消されます。自分では気づいていないだけで、部品が一部外れてしまっているかもしれません。
しかし、手入れや確認をしてもエラーが解消されないという場合は故障が考えられます。メーカーに問い合わせをするか、保証期間内であれば対象の修理会社に連絡をしてください。
電源が入らない
電気ストーブに限った話ではありますが、電源コードの断線には注意しましょう。
ストーブの電源が入らない、パネルも点灯していない、そんな時は電源系統の故障が疑われます。そういった故障で特に危険なのは電源コードの断線です。
コードが断線したままコンセントに指しっぱなしにしていると発火する恐れがあります。ストーブの設置場所はカーペットやソファの近くなど、燃えやすい家具が近場にある状態が多いかと思います。
火災が発生し大きな被害が出てしまわないよう早急に修理や処分を検討してください。
炎が安定しない
点火した炎が極端に弱い・強い場合は、ストーブの芯部分に異常が起こっている可能性が高いです。
まずストーブの火力が弱い場合ですが、芯が寿命を迎えている可能性があります。フィルターの掃除をすることで火力が戻ることもありますが、メンテナンスをしても状況が変わらないという場合は芯が劣化していると思われます。
芯を交換することで再び正常に使用できるようになるため交換の検討をしてください。
一方、炎が強く燃え上がり過ぎている場合は、不完全燃焼が起こっている危険があります。フィルターが汚れていたり、埃が詰まっていたりすると起こる現象ですが、不完全燃焼のまま点火し続けると一酸化炭素中毒になってしまう恐れがあり非常に危険です。
速やかに火を消して換気をしてください。換気が十分にされている状態で一度火をつけてみて、症状が変わらないようであれば、そのストーブを使用し続けることはできません。すぐにでも処分や買い替えを行ってください。
その他事象について
上記でご紹介をした事象以外にも、少しでも違和感を感じた場合は使用を中止してください。
異臭や異音がする、点火しづらい、燃料の減りが明らかに早くなった、などは部品の劣化やストーブ自体の寿命が近づいているサインです。
ストーブは危険性のある燃料を使用することから、ある程度の安全装置が実装されてはいますが、絶対に安全だとは言い切れません。
本記事でご紹介したストーブの処分方法も参考にしていただきつつ、ストーブに異変を感じたら修理や処分、買い替えを検討してください。
灯油・カセットボンベ・電池の処分について
灯油の処分
ストーブの捨て方をご説明する際に触れましたが、灯油に関してはストーブとは別で処分をしなければいけません。ストーブを処分する前に使い切ってしまえれば一番手っ取り早いですが、上手く使い切るというのも難しいものです。
だからといって、残った灯油を下水や河川に流したり、その辺の土に埋めるということは絶対にしないでください。環境汚染や水質汚染、生態系に悪影響を及ぼす危険性があります。
灯油の正しい処分方法については以下記事にて詳しく説明をしておりますので、ぜひ参考にしてください。
カセットボンベの処分
ガスストーブにカセットボンベを使用している場合は、カセットボンベをストーブから外して、ストーブとは別に処分をしなければいけません。
カセットボンベをセットしたままストーブを捨ててしまうと、回収をしてもらえない可能性もありますし、誤って回収された場合には爆発などの事故に繋がりかねません。
自分だけではなく大勢の人を巻き込んだ事態に発展する危険性もあるため、カセットボンベについては必ず外して、自己責任で処分をしてください。
電池の処分
ストーブの中には電池を使って動いているものもあります。電池に関しても、ストーブを処分する前に取り外して、ストーブとは別に捨てましょう。
電池は自治体のゴミ回収を利用して捨てることが可能です。電池ゴミや有害ゴミとして分別されていることが一般的ですが、お住まいの地域では何ゴミに分別されているのか確認をしてから捨ててください。
ストーブ側の絶縁対応も必要
ストーブ用に電池を使用するタイプの製品は、電池を外したあとに乾電池接続部の絶縁をしなければいけません。この絶縁を行っていなければ発火する恐れがあるためです。
特に石油ストーブは灯油を使う製品であるため、絶縁していない乾電池接続部から発火が起こってしまうと灯油に燃え移り大事故に繋がりかねません。
絶縁は、乾電池を入れる部分にセロハンテープを貼るだけで簡単に行えます。
絶縁せずに廃棄を行い悲惨な事故を起こさないよう、乾電池を利用している機種かどうかを確認し、必要に応じて絶縁を行ってください。
ストーブの処分にお困りなら『お助けうさぎ』にお任せください。
今回はストーブの捨て方・処分方法についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
ストーブの状態さえ良ければ売って利益を得ることも可能なため、ぜひ一度検討してみてください。売却とまではいかずとも、寄付したり譲ったりすることも可能でしょう。
ストーブが壊れてしまってゴミとして廃棄するしかないという場合は、不用品回収業者の利用をご検討ください。手間も時間も掛からず、手軽にストーブを処分することができます。
お助けうさぎは東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城を中心に不用品回収サービスをおこなっている会社です。ストーブの回収も承っております。灯油や電池、カセットボンベも回収可能なため、中身を抜いていただくなどといって手間は掛かりません。
不用品回収の他にも、粗大ゴミ回収・ゴミ屋敷清掃・遺品整理などあらゆるニーズにお応えいたします。ハウスクリーニングにも対応しておりますので、回収のついでに清掃をしてほしいというご要望にもお応えできます。
お助けうさぎの料金は分かりやすい定額パックをご用意しています。一番お得に処分できる金額でご提示いたしますので、余計な費用が掛かってしまうこともありません。
お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けておりますので、まずはお見積もりだけという方もぜひお気軽にご相談ください。ご相談とお見積もりは無料で承っております。
お助けうさぎの不用品回収サービスについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの「マンガと動画でわかるお助けうさぎ」をご覧ください。