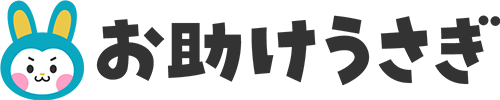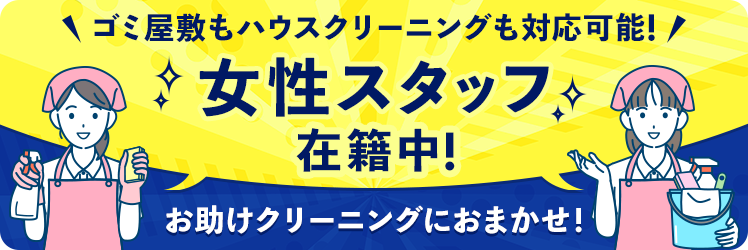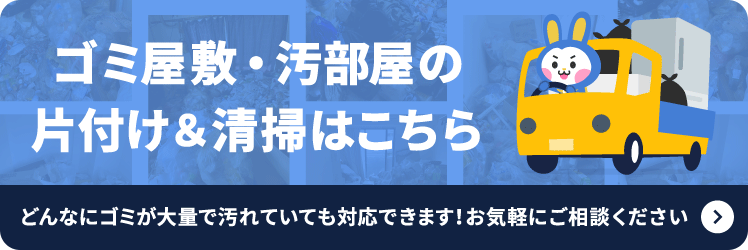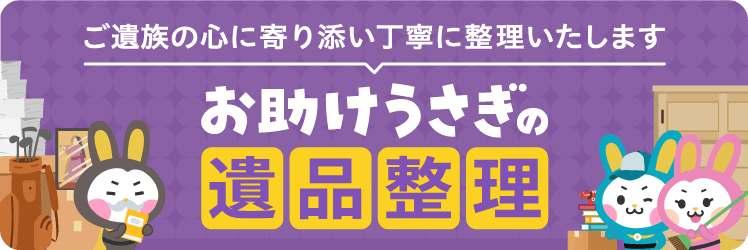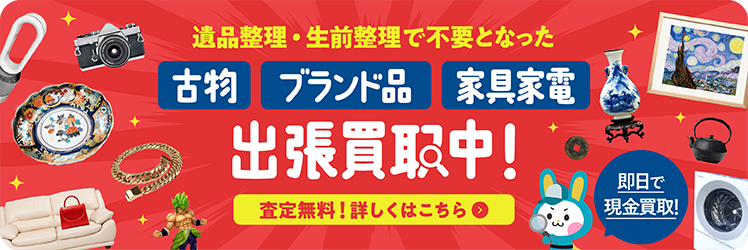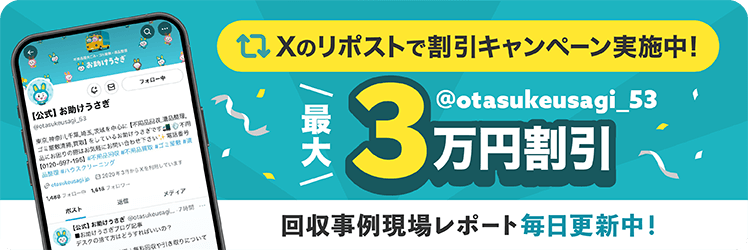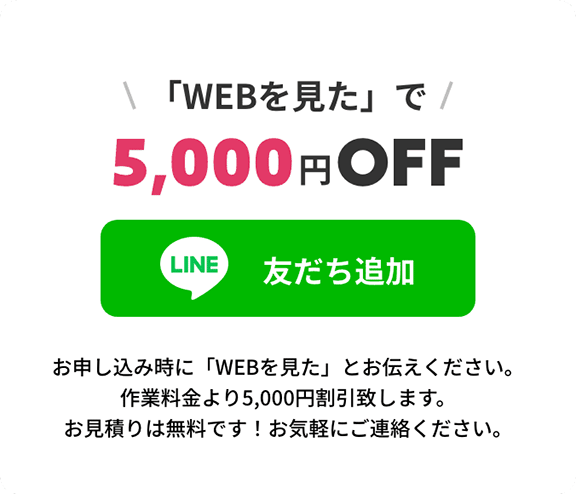土の捨て方7選|無料回収や引き取りについて詳しく解説
不用品別の処分方法「雛人形って処分をしてもいいの?」
「使わずに眠っている雛人形を手放したい!」
「捨てるのはもったいないので何かの役に立てたい」
女の子がいるご家庭では目にする機会も多い雛人形ですが、子どもが成長をして大きくなると、飾らなくなる日もいつかはやってきます。
人形はなかなか捨てづらい、処分方法が分からず物置にしまいっぱなしになっているというご家庭もあるのではないでしょうか。しかし、ずっと家に置いておくというのも難しいものです。
この記事では、雛人形の処分方法について詳しく解説していきます。
供養、寄付、譲渡、売却など、ただ処分するだけではなく今後のことも考えた方法も含めてご紹介していきます。
「雛人形を飾ることがなくなった」「処分したいけど迷っている」という人は、ぜひ参考にしてみてください。
【雛人形と一緒に、ご自宅の不用品もまとめてスッキリしませんか?】
\夏の5000円OFFキャンペーン実施中!/
詳細はバナーをタップしてお問合せください↓↓
この記事を読むと以下のことが分かります。
・雛人形について
・適切な処分方法
・処分する際の注意点
雛人形について
雛人形は3月3日に飾られる人形として有名ですが、古くは平安時代の「ひいな遊び」から始まったといわれています。「ひな人形」や「お雛様」と呼称されることもあります。
女の子の健やかな成長を願う行事として雛祭りがおこなわれ、子どもが成人した時にその役目を終えます。雛人形は子どもの厄を代わりに受けてくれる形代として意味をなしており、簡単に言えば人形のかたちをした「お守り」ということになります。
親や祖父母からすると子の成長を見守るうえで大切な行事のひとつとなりますが、子どもからすると自分のために綺麗で華やかな人形を飾ってもらえる日として印象深く、楽しい思い出になっていることでしょう。
雛人形の意味と並べ方
雛人形は男雛(おびな)と女雛(めびな)と呼ばれる対となった人形がきらびやかな装飾に囲まれていることが特徴的です。
結婚式を模した作りとなっており、華やかでありつつも重厚感があります。大型の雛人形であれば、男雛と女雛以外にも人形がたくさんならび、より楽し気な雰囲気の作りとなります。
人形たちにはそれぞれ立ち位置と意味があります。七段飾りの雛人形を例にして見てみましょう。
内裏雛(だいりびな)
配置:最上段
主役である二人、男雛と女雛のことを指し、最上段に飾ります。周囲にはぼんぼりや屏風、お神酒などが置かれ結婚式の華やかさを演出しています。
古くは男雛を向かって右側に座らせる左方上位(左側に座る人が格上)形式でしたが、時代の流れとともにそれも変わり、今は左側ではなく右側が上座という捉え方がなされ男雛は向かって左側に飾られるようになりました。これは昭和初期の天皇皇后両陛下の姿を映した写真に習ったものだと言われています。
しかしながら地域差もあるようで、一概にどちらの配置が正しいとは決められていません。
三人官女(さんにんかんじょ)
配置:二段目
女性を模した人形を三人並べて二段目に飾ります。女雛のお世話役として仕える女官を意味し、3人1組であることから三人官女と呼ばれています。
お酒を注ぐ役割もになっているため長柄銚子や盃を乗せた三方を持っています。真ん中に座る女官が年長者でリーダー的立場であり、眉がなくお歯黒姿をしていることが多いです。
五人囃子(ごにんばやし)
配置:三段目
楽器を手に持つ五人の人形です。三段目に飾ります。お囃子を奏でることで結婚式を盛り上げる役目を担っています。
向かって左から順に太鼓、大鼓、小鼓、横笛、謡とならんでおり、見た目も若く少年のような表情をしていることから元気で賑やかな場になることを表しています。
随身(ずいじん)
配置:四段目
武器を持った二人の人形であり、内裏雛を警護する役目があります。左大臣、右大臣とも呼ばれます。左大臣は年配者の見た目をしており知恵と経験のあるガードマン、右大臣は若者だが力に長けているガードマンとしてあらわされます。
二人の間には菱餅とお膳が置かれ、祝い席の華やかさを演出しています。
仕丁(しちょう)
配置:五段目
表情豊かな三人の人形で、それぞれ泣き顔、笑い顔、怒り顔をしています。泣くこともあれば怒ることもあるけれど、最後には笑っていられるといった人生感を表しています。庶民出身の労働者として仕えていることから、持っている道具も箒やちり取りなど親しみのある道具ばかりです。
三人の両端には桜の木と橘の木が飾られ、古くから日本で親しまれてきた花として結婚式を彩っています。
雛道具(ひなどうぐ)
配置:六段目、七段目
六段目には箪笥や鏡台など、昔ながらの婚礼家具が揃えられています。格式の高い武家の嫁入り道具を模しており、細かな装飾ときらびやかな見た目が印象的です。
七段目は籠や重箱、牛車(御所車)など嫁入りに向かうための道具が並べられます。大事な娘を大切に送り届けるといった願いが込められた道具です。
役割を終える時期
雛人形はお守りとして役割があり見た目も人の形をしているため、粗末な扱いは出来るかぎりしたくはないと感じることはよくあることです。
そうなると、雛人形はいつまで飾っておいたりする、いつまで手元に持っておくべきなのでしょうか。
飾っておく期間
雛人形を飾り始めるのは2月初旬~中旬頃、仕舞うのは3月3日を過ぎた後とされています。これらは明確に日付が決まっているわけではありません。
2月初旬から中旬は春を迎える季節であり、良縁にも繋がるともいわれ、女の子の将来を願ってこの時期に飾られます。また、2月3日の節分で厄を払った後に飾ると厄が寄り付かないともいわれています。
3月3日を過ぎると仕舞う時期を検討し始めなければいけませんが、急いで片付けなければいけないというわけではありません。目安としては4月中旬までであればいつでも良いとされています。
気を付けておきたい点として、片付ける日の天気には注意しましょう。出来るかぎり晴れた日に片付けることを心がけてください。
雛人形のパーツには布地が多く使用されています。湿気との相性が非常に悪く、湿気を含んだまま人形を箱に片付けてしまうと人形にカビが生えてしまうこともあります。水滴がシミとなって着物の見た目を損なってしまう可能性もあります。雛人形専用の除湿剤や調湿剤が販売されているほどです。
3月中旬から4月中旬までの間で、天気の良い日に、親子ともにゆっくりと丁寧に片付けられる日を作ってみてはいかがでしょうか。
手元に残しておく期間
雛人形は女の子の成長を願って飾るものです。したがって、成長をして自立をした時や結婚をして家を出た時が雛人形としての役割を終えた時ということになります。子どもの成長を見守ってくれて「ありがとう」という感謝の気持ちを込めて手放すようにしましょう。
ただし、手放す時期に関しても明確に決められているわけではありません。結婚をする際に子どもに持たせても良し、実家で飾り続けても良しとされています。
飾る場所がなくなってしまい箱に仕舞われたままになっているという場合は役目を終えたとして手放してもよいでしょう。壊れてしまったり汚れが酷くついてしまったという場合は、怪我の危険性や衛生面の観点から手元に置いておくことは推奨されません。
雛人形が役目を終えたあとも飾り続けるのか、それともお別れという意味で処分をするのかは、子どもの状況や雛人形の状態、家の状況によって変わってくるものでしょう。
そもそも処分をしてもよいのか?
人の形をしているものを捨てるのは気が引けると感じる方もいるかと思いますが、結論としては「雛人形は処分をしてもよい」とされています。
処分方法も多岐にわたり、自治体のゴミ収集に出すことも可能なのです。
しかし、長年大切に飾って子どもを見守ってくれた雛人形であることに変わりはないので、どんな処分方法を選択するにしても、処分前にまずは雛人形に対して感謝の意を伝えましょう。感謝を伝えることで役割を終えたという節目となり、自身の心の整理もできます。
また、ゴミとして廃棄するのではなく、供養をすることもできます。寄付やリサイクルをすることで雛人形を再活用してもらうことも可能です。
次より雛人形の代表的な処分方法を7つご紹介しますので、ご自身の気持ちと雛人形の状態を鑑みてどの方法を選択するか考えてみてください。
雛人形の処分方法7選
ここからは、雛人形の処分方法7つご紹介します。
雛人形の7つの処分方法
① 雛人形のご供養をお願いする
② 自治体のゴミ回収を利用する
③ 買取業者を利用する
④ フリマやオークションで売却する
⑤ イベント開催時に寄付をする
⑥ 福祉施設に譲る
⑦ 不用品回収業者に依頼する
前述でもお伝えした通り、雛人形は処分してはいけないという決まりがあるわけではありません。
ご自身の考え方に沿う方法を選ぶことはもちろん、雛人形の状態によって適切な処分方法は異なりますので、まずはどういった方法があるのかを確認してみてください。
あまりおいそれと捨てるものではないと慎重に考えてしまっていては、それこそ処分困難な不用品と化してしまいますので、ネガティブに考えすぎずに処分を進めてみましょう。
① 雛人形のご供養をお願いする
長年成長を見守ってくれた大切な雛人形をただ処分するのは悲しい、気が進まないという方は、ぜひ供養をするかたちで手放してみてはいかがでしょうか。
人形供養は、雛人形に感謝の気持ちを伝えるとともに、安らかにその役目を終えてもらえるための行為となります。供養をすることで心の整理もでき、気持ちの切り替わりにもなります。
人形供養をする方法は様々あります。代表的な方法を2つご紹介しますので検討をしてみてください。
自分でお寺や神社にご供養を依頼する
雛人形の供養をしてくれるお寺や神社は全国にたくさんあります。インターネットで人形供養を実施しているお寺や神社を探してみましょう。
予約制のところもあれば、予約なしで持ち込める寺社もあるので、寺社に持っていく前に申し込み方法や予約の有無を確認しておきましょう。また、供養には供養料が必要となります。金額は寺社により異なりますが、5千円~1万円程が相場となっています。
供養方法も様々あり、寺社にお任せする方法や、その場で一緒に供養をする法要形式をとっているところ、雛人形にお礼状を書くことができるところなどもあります。自分の理想のかたちで供養ができるように、どの寺社で供養をするか慎重に検討を進めてみてください。
以下は雛人形の供養ができる寺社の一例です。
| 名称 | 特徴 | 供養料 |
| 長福寿寺(千葉県) | ・3ヵ月間の読経供養後に火葬 ・雛壇も一緒に供養可能 ・宅配での依頼も可能 | 五段飾りまで:一式1万円 七段飾り以上:一式2万円 |
| 本寿院(東京都) | ・参列可能な公開供養 ・事前予約は不要 ・宅配での依頼も可能 | 5千円~(人形の個数により変動) 個別読経供養を希望する場合は一組3万円 |
| 玉村八幡宮(群馬県) | ・毎月10日15時に供養 ・人形のみ供養可能 ・宅配での依頼も可能 | 人形1体の場合:千円 複数体の場合:3千円~5千円 |
直接人形を持っていくことも可能ですが宅配での供養依頼も受け付けている場所があります。大型の雛人形を運搬するのは困難だという場合は宅配受付をしている寺社を探してみましょう。
人形供養代行サービスを利用する
供養をおこなうお寺や神社が近場にないという方や供養に行く時間がとれないという方に向けて、供養を代行しておこなってくれるサービスがあります。
基本的にはインターネットや電話で申し込みをした後に郵送で雛人形を送るかたちとなるため、供養可能な寺社を探したり持ち込んだりといった手間がかかりません。
以下は代行サービスの一例です。
| 業者名 | サービス名 | 料金 |
| 一般社団法人日本人形協会 | 人形感謝(供養)代行サービス | 段ボール1箱5千円 別途郵送料 |
| 花月堂 | 人形供養祭 | 2千円~9千円 段ボールのサイズにより異なる |
| 株式会社クラウドテン | みんなのお焚き上げ | 6千円~1万7千円 段ボールのサイズにより異なる |
郵送した人形は、提携している寺社にて供養されることとなります。
ただし、供養する日時を自身で決めることはできません。1年に1回や数ヶ月に1回など業者側と寺社側で日時を決めて合同で供養がおこなわれます。この機会を逃してしまうと、翌年まで供養がされないということにもなりかねませんので注意しましょう。
サービスごとに提携している寺社や供養方法が異なりますので、まずはホームページ見て自分の希望通りの供養をしてもらえるかどうか確認しておきましょう。
まず何よりも先に不要を考えよう。
雛人形の処分はどうしても気持ちの面の比重が大きくなる傾向が強いです。そのため、どのような形であれ供養を行っていけば、決して間違った方法での処分とはならないでしょう。
人の形をした人形はどうしても想いや念がのり移りやすいものでもあるので、考えすぎてしまっても決しておかしなことではないでしょう。
② 自治体のゴミ回収を利用する
雛人形の処分方法にこだわりがない場合は、自治体のゴミ回収を利用して処分することも可能です。
自治体によって細かな規定は異なりますが、人形単体であれば可燃ゴミや不燃ゴミなどの普通ゴミとして無料で回収してもらうことができます。台座含めた雛人形セットや大型の人形となると粗大ゴミ扱いになる可能性があります。
普通ゴミとして出す
雛人形単体や、雛人形のパーツの一部だけを処分したい場合は、普通ゴミとして出すことができますので、自治体のゴミ分別ルールに従い処分をしましょう。
分別ルールさえしっかりと守れば、他の家庭ゴミと一緒にまとめてゴミ袋に入れて処分をすることが可能です。掛かる費用はゴミ袋代だけであり、回収自体は無料でおこなってもらえます。
雛人形をそのままゴミ袋に入れると見た目が気になってしまうという場合は、紙や新聞紙などで雛人形を包んでゴミ袋に入れても問題ありません。
粗大ゴミとして出す
粗大ゴミの判定基準は一辺の長さが30cmを超えるかどうかです。
屏風などの付属品や、台座やガラスケースなどの分解できないもので一辺が30cmを超えるものは粗大ゴミ扱いとなります。
粗大ゴミとして雛人形を処分する場合、定められた手続きと料金に従って処理をします。粗大ゴミ回収の予約をして所定の店舗で粗大ゴミ処理券を購入し、回収日時当日は雛人形に粗大ゴミ処理券を貼り付けて指定の回収場所に出せば処分完了です。
粗大ゴミ処理券の購入は自己負担となり、誤った処理券を購入して雛人形に貼り付けてしまうと回収してくれなくなってしまう場合があるので、予約をした際にしっかりと処理券の種類と値段を確認し、正確に購入をしましょう。
③ 買取業者を利用する
人形や骨董品に詳しい鑑定士が常駐していて人形の買い取りをおこなっている業者であれば雛人形を買い取ってもらうことができます。買い取ってもらえるのであれば処分費用は無料であり、お金を得ることもできます。
お持ちの雛人形の作家が有名な名匠であったり、人気の老舗メーカー製造のものであったりする場合、買取をしてくれる可能性が高いです。雛人形に目立つ傷がついていたり、パーツが足りなかったりすると買い取りを断られる可能性もありますので気を付けましょう。
また、査定方法や査定額は業者によって異なります。店頭買取のみ対応している場合もあれば、出張買取をしてくれる業者もあります。
雛人形が売れるかどうか心配な場合は、写真で概算査定をしてくるサービスをおこなっていたりするので、お近くに買い取り業者があるのかどうか、雛人形を持ち運べるのかどうか、作者やメーカーを自分で特定できるかどうかを考慮して、買い取り業者を選んでみてください。
買取業者を利用するときはタイミングも考慮する必要があります。
雛人形はとても季節性が高く、求められるのは一年のうちでも非常に限られた期間のみです。1番ニーズが高まるのは年始から2月頃です。
買い取り業者もその時期めがけて買い取り強化をおこなうので、買い取り業者を利用するのであれば年末年始のタイミングを狙うとよいでしょう。
ひな祭りの時期を過ぎてしまうと一気にニーズは低迷するので注意が必要です。
タイミングを見て売りに出す場合は、保管している間に雛人形が劣化してしまわないよう注意しなければいけません。
④ フリマやオークションで売却する
雛人形を個人間で売買することも可能です。フリマアプリやオークションサイトを使用することで、全国の人相手に売却を勧めることができます。
ファンやコレクターのニーズに沿ったものであれば、高値で売れる可能性もあります。
ただし、業者を介さない個人間での取引となるので、必ずしも買い取り手がつくとは限らないこと、トラブルに発展してしまわないよう配慮する必要があることは頭に入れておきましょう。
フリマアプリやオークションサイトには雛人形だけでも数百体は出品されており、設定価格も様々です。買い取り希望者のニーズにうまく沿うことができるよう、出品時期や出品情報は考慮する必要があります。
また、出品情報は正確かつ詳細に記載をしましょう。
いざ買い手がついた際の梱包や郵送は自分でおこなうこととなるので手間はかかりますが、売却することで収入になるというのは嬉しいポイントです。
雛人形は繊細で衝撃には非常に弱いです。梱包をする際は緩衝材を利用して雛人形を揺れから保護できる状態にしておくことが重要となります。
⑤ イベント開催時に寄付をする
雛人形は家庭でのひな祭りに使用できるだけでなく、全国各地で開催されるひな祭りイベントにも使用されています。
イベントに使用される雛人形は各家庭で不要となったものを募るという形式が多く、雛人形の処分を検討している際に利用してみてはいかがでしょうか。
代表的なイベントとして、徳島県勝浦町のビッグひな祭りでは、各方面から集められた雛人形が100段の階段に積み上げられ、その高さは最大8メートルもなるというスケールの大きいひな祭りとして人気があります。その歴史は1988年4月に始まり、日本最大のひな祭りとして有名です。
他の地域でも同様のイベントを行っており、賑わいを見せています。
・かつうらビッグひな祭り(千葉県)
・鴻巣びっくりひな祭り(埼玉県)
・南紀勝浦ひなめぐり(和歌山県)
・信州須坂ハッピーひなまつり(長野県)
こういったイベントへ雛人形を寄付したいという時は、イベントの公式ホームページや自治体のホームページを確認し、申し込みをする必要があります。
申し込み時期はイベントごとに事なり、申し込み可能日時が限定されている場合や、募集受付数に制限を設けている場合もあるので早めに確認をしておきましょう。また、寄付をする際に供養料や保管料がかかる場合があります。
無料での寄付とはならないものの、イベントに自身の雛人形が使用され、多くの方に楽しんでもらうことができる素敵な社会貢献といえるでしょう。
イベント終了後はイベント開催者側で供養を行い処分をしてくれるので安心です。
寄付した雛人形が飾られているところを観光ついでに見に行き楽しむこともできます。イベントを盛り上げる手伝いができるだけでなく、自身の思い出にもなるのは嬉しいポイントです。
⑥ 福祉施設に寄付をする
保育施設、高齢者施設、障がい者施設などの各種福祉施設では、雛人形の寄贈を募っている場合があります。
施設内で行われるイベントに用いられることとなるので、ただ処分するのではなく再利用してもらえる方法として検討してみてもよいでしょう。
寄贈方法は施設ごとに異なります。施設で直接募集をかけている場合もあれば、自治体を通して募集していたり、支援団体を通して募集していたりします。お近くの施設で雛人形の寄贈を募っているかどうかインターネットなどで調べてみましょう。
寄贈をする際の梱包や運搬は基本的に自分でおこなうこととなり、料金が発生する場合もあるので、そこも考慮した上で福祉施設への寄贈を検討してみてください。
福祉施設への寄付をする際は雛人形の衛生状態が重要視されます。寄贈する前に人形や台座などを綺麗にしておきましょう。
⑦ 不用品回収業者に依頼する
雛人形の処分方法にこだわりがない方で、出来るだけ手軽に処分をしたいと考えている方は不用品回収業者に依頼をして雛人形を回収してもらいましょう。
特に、人形の数が多い場合や大型の雛人形をお持ちの方にはおすすめの方法です。
自治体の粗大ゴミ回収に比べて手続きが簡単で柔軟です。24時間オンライン予約を受け付けている業者もあり、都合の良い日を申告して回収日を調整することができます。
回収作業は業者のスタッフに一任できるため、自分で分別や梱包をしたり運搬をしたりする必要はありません。破損していたり汚れが酷かったりする雛人形でも問題なく回収してくれるので、人形の状態を気にする必要もありません。
有料とはなりますが、手間のかからない楽な方法と言えるでしょう。
処分方法別の注意点

雛人形の処分方法についていくつかご紹介してきましたが、注意点も合わせて確認しておきましょう。
▼寺社でご供養をお願いする場合
・お寺や神社ごとに受付方法が異なります。持ち込みか郵送か確認が必要です。
・ご供養方法も異なります。法要、お焚き上げ、個別供養などがあります。
・ケースやひな壇、屏風などの付属品は受け入れていない場合があります。
▼寄付・譲渡・売却をする場合
・綺麗な状態で保管されている雛人形に限ります。破損している場合は別の方法を検討してください。
・必ずしも受け取り手が見つかるとは限りません。
・期間限定で募集している場合があります。
▼自治体や業者を利用して処分する場合
・処分が目的となるので、供養はされません。
・自治体の無料回収を利用することができます。
・業者への依頼は相応の費用が発生します。
雛人形の処分は、ご自身の考え方と雛人形の保管状態を考慮して選ぶことになるので、どの処分方法が最適なのか検討をしてみてください。
ご自身が優先するのは供養や再利用なのか、処分スピードなのか、費用面なのか、考えてみましょう。
雛人形を処分する前に一度飾ろう
雛人形を処分するまでに時間的に余裕がある場合は、最後の思い出として一度飾ってあげることをおすすめします。
子どもが成長するまで見守り、長年役目を果たしてきた人形たちに感謝を伝えましょう。簡易的な供養という意味にもなります。
また、雛人形を処分する前の最後の確認作業としても意味があります。雛人形を保管していた箱の中に、手紙や写真など大切なものが入っているかもしれません。
名前札がある場合は寄付や売却をしてしまわないよう取り除いておく必要があります。個人情報に関連するものはすべて人形と別にしてから、処分を進めてください。
汚れをできるだけ取り除いて保管をしよう
雛人形が役目を終える日のことも考えて、保管をする際はできるだけ汚れを取り除くようにしてください。
雛人形はとてもデリケートですので、なんの手入れもせずに保管をしてしまうと汚れの蓄積や虫食いで飾れなくなってしまうだけでなく、処分方法の選択肢も狭まってしまいますので気を付けましょう。
また、お手入れ仕方にも気を付ける必要があります。
人形の顔や紙などに手で直接触れることは推奨されません。皮脂や手あか、指紋が付着してしまい劣化の原因となってしまいます。
雛人形を購入した際に布手袋が付属品として同梱されていることが多いので、お手入れの際には必ず着用をしましょう。同梱されていない場合は、市販の手入れキットを購入することをおすすめします。
手入れの際に強く擦ったり、目の粗い布で拭いたりすることも推奨されません。
羽箒のような柔らかい素材で軽く埃を払ったり、汚れが気になる箇所は筆を使って払ったりすることで損傷や劣化を避けることができます。
そのほかに、湿気にも注意しましょう。カビの原因ともなりますので、天気の良い日に雛人形を箱にしまったり、乾燥材や防虫剤を利用したりすることで劣化を防ぐことができます。
人形以外のパーツの処分方法
雛人形にも色々と種類があり、木製の台座の上に人形を2体飾る小型のものや、ガラスケースに入ったもの、五段飾りや七段飾りなどスチール製のひな壇を利用するものなど多種多様です。
売却や寄付といった処分方法であれば人形以外のパーツも含めて手放すことができますが、廃棄品として捨てる場合はお住いの自治体の分別ルールをしっかりと確認しておきましょう。
木製の台座であれば可燃ゴミとして捨てることができます。ガラスケースの場合は不燃ゴミ、スチールパーツの場合は不燃ゴミもしくは金属ゴミなどで捨てることができますが、サイズには注意しましょう。
サイズが30cmを超える場合は粗大ゴミで捨てなければいけない可能性があります。30cmはあくまでも目安であり、自治体によって粗大ゴミの規定サイズは異なりますので事前に確認をしておくと安心です。
人形やパーツごとに分別するのは面倒だと感じる場合は、不用品回収業者を利用して全て一括で回収をしてもらいましょう。不用品回収業者であればどんな素材のものでも分別や梱包不要で回収をしてくれます。
雛人形を台座含め丸ごと廃棄しなければいけないという場合、細かく分別してゴミ回収に出すか不用品回収を利用するかを検討して処分方法を決めましょう。
雛人形の処分は『お助けうさぎ』におまかせ!

今回は雛人形の捨て方・処分方法と、処分に関連する情報をご紹介いたしました。
雛人形の処分には様々な選択肢があります。
思い入れのある雛人形であればご供養をしてお別れをすることをおすすめしますが、ご自身の状況や雛人形の状態に応じて処分方法を選ぶことができるので、気負わず、やりやすい方法で処分をしましょう。
雛人形の処分に手間をかけたくない場合や、引っ越しや遺品整理などで他の不用品とあわせて雛人形を処分しなければいけなくなったという場合は、お助けうさぎの不用品回収サービスをご利用ください。
『お助けうさぎ』は東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城を中心に不用品回収サービスをおこなっている会社です。
雛人形本体だけでなく、ケースや台座、ぼんぼり、毛せんなど、付属品も一緒に処分可能です。小型のものから大型のものまでサイズも問いません。その他にも、粗大ゴミ回収・ゴミ屋敷清掃・遺品整理などあらゆるニーズにお応えいたします。
料金は分かりやすい定額パックをご用意しています。一番お得に処分できる金額でご提示いたしますので、余計な費用が掛かってしまうこともありません。
お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けておりますので、まずはお見積もりだけという方もぜひお気軽にご相談ください。ご相談とお見積もりは無料でおこなっております。
『お助けうさぎ』のサービスについて更に詳しく知りたい方はこちらの「マンガと動画でわかるお助けうさぎ」も併せてご覧ください!