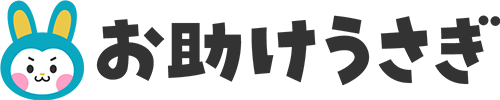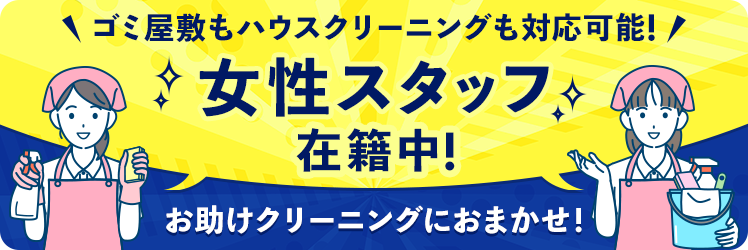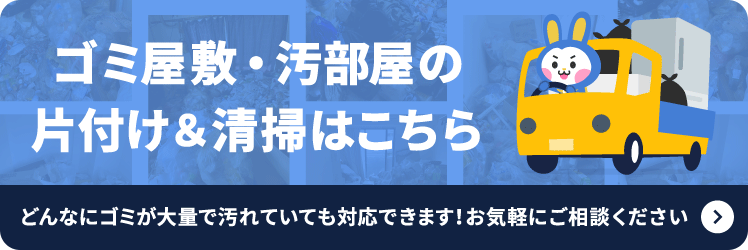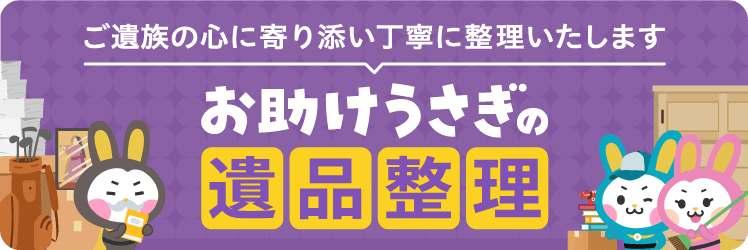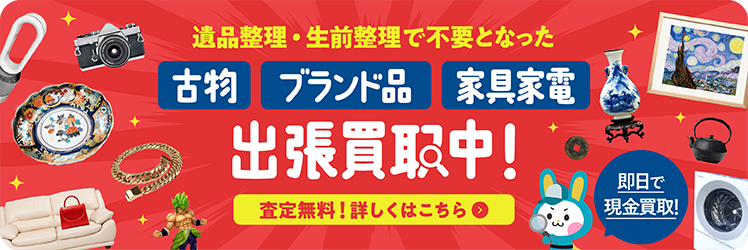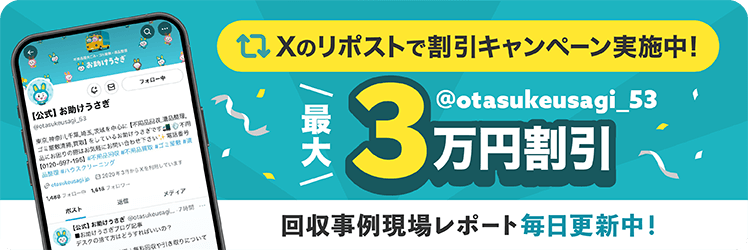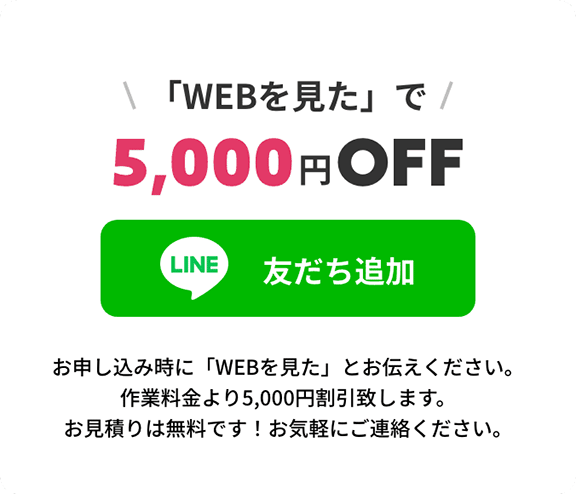土の捨て方7選|無料回収や引き取りについて詳しく解説
不用品別の処分方法「この大きな発泡スチロール、普通ゴミでいいのかな?」
「大量に溜まってしまい、捨てるのが面倒…」
「引越しで出た不用品と一緒に、手間なく処分したい!」
私たちの生活に欠かせない便利な素材、発泡スチロール。しかし、いざ捨てようとすると、その方法に迷った経験は誰にでもあるはずです。軽くてかさばる上に、自治体によって分別ルールがバラバラで、どうすれば良いか分からなくなってしまいますよね。
ふたを開ければ奥が深い、発泡スチロールの処分方法。
この記事では、そんなお悩みをすべて解決するため、不用品回収のプロが持つ知識を総動員して、発泡スチロールの捨て方を網羅的に解説します。
基本的な自治体のルールから、かさばる発泡スチロールを劇的に小さくする裏ワザ、捨てる以外の賢い再利用法、そして手間をかけずに今すぐ処分したい場合の最適な方法まで、この記事一枚で全てが分かります。
発泡スチロールの捨て方が気になっている方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むと以下のことが分かります。
・すぐに分かる、7つの最適な捨て方
・【東京23区】最新の公式分別ルール一覧
・かさばる悩みを解決する、簡単な縮小テクニック
・捨てるのはもったいない!驚きの再利用アイデア
・費用・手間・スピードで比較する、あなたにピッタリの処分方法
・プロが教える、処分の際の注意点と豆知識
発泡スチロールのおすすめの捨て方7選

こちらでは、発泡スチロールのおすすめの捨て方を7つご紹介します。ゴミとして自治体に回収してもらう方法から、もっと手軽に、あるいはエコに処分する方法まで、様々な選択肢が存在します。ご自身の状況や発泡スチロールの量に合わせて、最適な捨て方を検討してみてください。
① 自治体の普通ゴミとして捨てる
最も基本的で、費用を抑えられる方法です。お住まいの自治体が定める「可燃ゴミ」「資源ゴミ」「プラスチックゴミ」などの分類に従い、指定の曜日に出します。無料で回収してもらえるので、少量の場合には一番おすすめの方法です。
ただし、自治体によって分類やゴミ出しの日が異なるため、必ずお住まいの地域のルールを確認する必要があります。また、後述するように大きさや汚れの有無によっても出し方が変わるため、注意が必要です。
② 自治体の粗大ゴミとして捨てる
自治体が定める規定サイズ(一般的には一辺が30cmや50cm以上)を超える大きな発泡スチロールは、普通ゴミではなく「粗大ゴミ」として捨てる必要があります。
粗大ゴミとして出す場合は、事前に自治体へ申し込み、有料の処理券を購入して貼り付ける必要があります。費用も手間もかかってしまうため、自分で小さく切断して普通ゴミとして出せるのであれば、そちらの方が経済的です。どうしても切断が難しい、巨大な塊である場合などの最終手段と考えましょう。
③ スーパー等の資源回収ボックスへ投入する
肉や魚などの食品が入っていた発泡スチロール製のトレイは、多くのスーパーマーケットや公共施設で無料回収してくれます。施設の入り口付近に「資源回収ボックス」が設置されていることが多いです。
買い物ついでに捨てられるので非常に便利ですが、いくつか注意点があります。
- 必ずキレイに洗って乾かすこと: 汚れたままではリサイクルできないため、洗浄と乾燥が必須です。
- トレイ以外のものは入れないこと: 回収対象は基本的に食品トレイのみです。梱包用の緩衝材などは入れられません。
- すべての店舗にあるわけではない: あくまで店舗側の自主的な取り組みのため、設置されていない場合もあります。
④ 購入店に回収・引き取りを依頼する
家電などの製品を購入した際に緩衝材として入っていた発泡スチロールは、購入したお店で回収してくれる場合があります。特に、配送と設置を同時に依頼した場合は、作業員がその場で出た梱包材をすべて持ち帰ってくれるサービスが多くあります。
自身で店舗に持ち込む場合も、対応してくれる可能性があるので、一度問い合わせてみると良いでしょう。ただし、全ての店舗や配送会社が対応しているわけではないため、事前の確認は必要です。
⑤ 緩衝材として再利用する
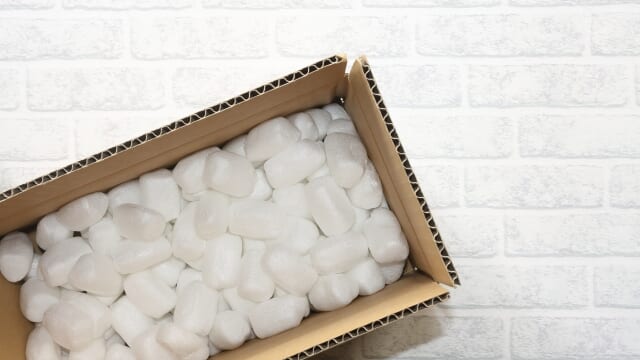
処分するのではなく、再利用するのも賢い方法です。特に、商品を衝撃から守るために使われていた梱包用の発泡スチロールは、緩衝材として非常に優秀です。
フリマアプリで商品を発送する際や、引っ越しの荷造りで割れ物を梱包する際に活用できます。無料で手に入る梱包材として、費用をかけずに手放せる(活用できる)のが魅力です。汚れや匂いがなく、置き場所に困らない場合は、いざという時のためにストックしておくと便利です。
⑥ 断熱材として再利用する
あまり知られていませんが、発泡スチロールは断熱性に非常に優れています。その性質を利用して、家庭の省エネ対策に活用できます。
薄い板状の発泡スチロールを窓際に設置することで、冬は外からの冷気を遮断し、夏は室内の冷気が逃げるのを防ぎ、冷暖房の効率をアップさせます。特に湿気に強い性質は、結露しやすい窓辺で使う際に段ボールよりも優れています。遮光性も高いため、光を入れたくない倉庫や食糧庫の窓に設置するのも良いでしょう。
⑦ 不用品回収業者に依頼する
「大量の発泡スチロールを一度に処分したい」
「引越しで出た他の不用品と一緒に捨てたい」
「分別や洗浄がとにかく面倒」
そんな時は、不用品回収業者に依頼するのが最も便利でスピーディな方法です。
自治体のゴミ回収とは異なり、日時の指定が自由で、梱包や運び出しといった面倒な作業もすべてスタッフに任せられます。洗浄や解体が不要なため、手間なく時短で処分できるのが最大のメリットです。費用はかかりますが、手間と時間を買うと考えれば、非常に価値のある選択肢です。
自治体で処分する|東京23区の分別ルールを徹底解説
発泡スチロールの分別は、お住まいの自治体によってルールが大きく異なります。ここでは、特にルールの違いが複雑な東京23区を例に、最新の公式情報に基づいた捨て方を詳しく解説します。
23区で分別ルールが違う理由
家庭で出るごみの中でも、特に処分方法に迷いやすいのが「発泡スチロール」です。
かさばる上に、自治体によって分別ルールが大きく異なるため、多くの住民が混乱を経験します。ある区では「資源」として回収されるものが、隣の区では「燃やすごみ」に分類されることも珍しくありません。この複雑な状況を理解するためには、まずルールが異なる根本的な理由を知ることが重要です。
第一に、最も大きな要因は各区の廃棄物処理インフラの違いにあります。発泡スチロールを資源として再利用するには、回収後にそれを溶かして再びプラスチック原料(ペレット)に戻すための専門施設が必要です。区が直接または委託契約を通じてこうした処理施設を利用できる場合、発泡スチロールは「資源」として分別されます。一方で、そうした設備を持たない、あるいは契約していない区では、焼却処理するしかなく、「燃やすごみ」として扱うことになります。つまり、各区のルールは、単なる方針の違いではなく、物理的・契約的な制約に根差しているのです。
第二に、「発泡スチロール」と一括りにできない種類の多様性も、ルールを複雑にする一因です。家庭から出る発泡スチロールは、その用途によって大きく3つの階層に分けて考えることができます。
- 食品トレイ: 肉や魚、惣菜などに使われるトレイは、素材がポリスチレン(PS)で均一なため、リサイクル価値が非常に高い品目です。このため、多くの区ではスーパーマーケットの店頭回収(拠点回収)など、特別なルートで回収されています。
- 梱包材・緩衝材: 家電製品などを購入した際に入っている箱型のものや詰め物です。これが最も分別に迷うカテゴリーであり、その扱いは区の処理能力に完全に依存します。例えば港区では資源ですが、世田谷区では燃やすごみとなります。
- 発泡スチロール製品: クーラーボックスや発泡スチロール製の畳など、商品そのものが発泡スチロールでできているものです。これらは「容器」や「包装」ではないため、多くの場合、サイズに応じて一般のプラスチック製品や粗大ごみとして扱われます。
最後に、東京23区のプラスチックリサイクルは、現在大きな過渡期にあるという点を認識しておく必要があります。地球環境への配慮の高まりを受け、これまで焼却していたプラスチック類を資源として回収する動きが活発化しています。墨田区、大田区、文京区など、近年プラスチックの一括回収を新たに開始、または予定している区が複数存在します。これは、分別ルールが今後も変更される可能性があることを示唆しています。
本稿では、こうした背景を踏まえ、東京23区すべての自治体ウェブサイトの情報を徹底的に調査し、発泡スチロールの捨て方に関する最新かつ詳細なルールを一覧にまとめました。このガイドが、日々の正しいごみ分別の一助となることを目指します。
東京23区 発泡スチロール分別・処分方法一覧表
以下に、東京23区それぞれの発泡スチロールの分別ルールをまとめました。ご自身の区のルールを確認し、正しい処分を心がけてください。
| 区 | ごみの分類 | 出し方の要点 | 粗大ごみになるケース | 備考・注意事項 |
| 千代田区 | プラスチック | ・透明または半透明の袋に入れる。 ・他のプラスチック類(袋、パック、ボトル類)と一緒に出す。 ・汚れに関する具体的な記述はないが、一般的に洗浄が推奨される。 | ・区のウェブサイトに明確な記述なし。一般的なプラスチック製品の粗大ごみ基準(一辺30cm以上)が適用される可能性が高い。 | ・一部情報源では「燃えるごみ」と記載があるが、区の公式情報では「プラスチック」と分類されているため、公式情報を正とする。 ・出典: 千代田区公式ウェブサイト |
| 中央区 | プラスチック (有料の場合あり) | ・食品用発泡スチロールトレイは拠点回収も実施。 ・梱包用の緩衝材などは「容器包装プラの日」に、透明または半透明の袋に入れて出す。 ・大きいものは袋に入る大きさに割って(切って)出す。 ・汚れが落ちないものは「燃やすごみ」。 ・魚箱など特定の箱は1箱につき10Lの有料処理券が必要な場合がある。 | ・プラ製容器包装として出せない製品(おもちゃ等)で、50cm以上のものは粗大ごみ。発泡スチロールの梱包材自体に関する明確な基準はない。 | ・食品トレイと梱包材で出し方が異なる点に注意。 ・有料のケースがあるのは23区内では珍しいルール。 ・出典: 中央区公式ウェブサイト, 中央区ごみ分別辞典 |
| 港区 | 資源プラスチック | ・軽くすすぐか、古布などで拭き取って汚れを落とす。 ・中身の見える袋か、ふた付きの容器に入れる。段ボール箱や紙袋は不可。 ・他の資源プラスチックと一緒に出してよい。 | ・発泡スチロールは30cmを超えても粗大ごみにならない。これは港区の特筆すべきルール。 ・ただし、硬く頑丈なプラスチック製品(ビールケース等)は60cm未満でも粗大ごみになる場合がある。 | ・サイズに関する例外ルールが最も重要なポイント。 ・出典: 港区公式ウェブサイト |
| 新宿区 | 資源プラスチック | ・「容器包装プラスチック」と「製品プラスチック」を一つの袋にまとめて出す。 ・汚れが取れないものは「燃やすごみ」。 ・100%プラスチック素材のものが対象。 | ・一辺の長さが30cmを超える場合は「粗大ごみ」。 | ・発泡スチロールは「容器包装プラスチック」に分類される。 ・出典: 新宿区公式ウェブサイト |
| 文京区 | 可燃ごみ (例外あり) | ・発泡スチロールの箱・緩衝材は「可燃ごみ」。 ・可燃ごみとして出す場合、1個につき10Lの有料処理券が必要。 ・例外: 食品用発泡スチロールトレイは、拠点回収または可燃ごみとして出せる。 | ・区のウェブサイトに明確な記述なし。一般的な粗大ごみ基準(一辺30cm以上)が適用される可能性が高い。 | ・発泡スチロールの箱・緩衝材は「可燃ごみ」として有料で出す、という点が重要。 ・食品トレイは軟質の「つまようじが刺さるもの」が対象。 ・出典: 文京区公式ウェブサイト |
| 台東区 | プラスチック | ・発泡スチロールの箱・緩衝材は「プラスチック」として回収。 ・水で軽くすすぐか、古布で拭って汚れを落とす。 ・汚れがひどい場合(べたつき、強いにおい)は「燃やすごみ」。 ・透明または半透明の袋か、ふた付きの容器に入れる。 | ・一番長い部分が30cmを超えるものは「粗大ごみ」。 | ・以前は有料処理券が必要だったが、現在はプラスチックとして分別回収されている。 ・出典: 台東区公式ウェブサイト |
| 墨田区 | 資源物(プラスチック) | ・軽くすすぐか汚れを拭き取る。 ・他のプラスチック類と一緒に、中身の見える袋に入れて出す。 ・二重袋にしない。 | ・一辺の長さが概ね30cmを超えるものは「粗大ごみ」。 | ・令和5年10月からプラスチックの一括回収が開始された。 ・出典: 墨田区公式ウェブサイト |
| 江東区 | 資源 or 燃やすごみ (種類による) | ・「つまようじが簡単に刺さる」発泡トレイや緩衝材は「資源の日」に回収。 ・軽くすすいで汚れを落とし、専用コンテナか袋に入れる。 ・刺さらない硬いプラスチック容器や、汚れが落ちないものは「燃やすごみ」。 | ・おおむね一辺が30cm以上のものは「粗大ごみ」。 | ・「つまようじテスト」というユニークな判別方法が最大の特徴。 ・プラマークが付いていても、ようじが刺されば「資源の日」に出すという区独自の優先ルールがある。 ・出典: 江東区公式ウェブサイト |
| 品川区 | 資源(プラスチック類) | ・発泡スチロールは「資源」として回収。 ・汚れを落として出す。汚れがひどい場合は「燃やすごみ」。 ・細かくして袋に入れて出すことが推奨されている。 ・他のプラスチック類と一緒に出す。 | ・一辺の大きさが30cmを超えるものは「粗大ごみ」。 ・発泡スチロール製の畳などは粗大ごみとして有料で回収される例がある。 | ・発泡スチロール製の製品(家具など)は粗大ごみになる場合がある点に注意。 ・出典: 品川区公式ウェブサイト |
| 目黒区 | 資源(プラスチック) | ・プラマークの付いた発泡スチロール(緩衝材など)は「資源」。 ・中身が見える袋に入れて出す。 ・汚れがひどい場合は「燃やすごみ」。 | ・最長辺がおおむね30cm以上のものは「粗大ごみ」に該当する可能性がある。 ・ただし、細かく砕いたり切断したりして袋に入れば資源として出せる。 | ・紙製の緩衝材(卵パックなど)は「可燃ごみ」。 ・出典: 目黒区公式ウェブサイト |
| 大田区 | プラスチック | ・発泡スチロール、食品トレイは「プラスチックの日」に回収。 ・大きいものは、可能な限り袋に入る大きさに砕いて出す。袋の中で砕くと飛び散らない。 ・砕けない場合は袋に入れずそのまま出してもよい。 ・汚れ(特にねばねば)が残っている場合は「可燃ごみ」。 | ・一辺が30cm以上のものは「プラスチックの日」の回収対象外。 ・区は「大きな発泡スチロールゴミは粗大ごみの対象として案内していない」としており、細かくして一般ごみとして出すよう求めている。 | ・令和7年4月1日からプラスチックの一括回収が本格開始。 ・30cmを超えても粗大ごみではなく、砕いて出すというルールが特徴。 ・出典: 大田区公式ウェブサイト |
| 世田谷区 | 可燃ごみ (例外あり) | ・基本的には全て「可燃ごみ」として出す。 ・大きなものは小さく切り分けて可燃ごみ袋に入れる。 ・例外: 食品トレイは区内の拠点回収も利用可能。 | ・最も長い辺が30cmを超えるプラスチック「製品」は粗大ごみ。 ・ただし、梱包用発泡スチロールは大きくても切って可燃ごみに出すのが基本。 | ・原則「燃やす」という分かりやすいルールだが、環境配慮派のために食品トレイの資源回収ルートも残されているハイブリッド型。 ・出典: 世田谷区公式ウェブサイト |
| 渋谷区 | 資源(プラスチック) | ・発泡スチロールは「資源」として回収。 ・食品用トレイはきれいに洗って出す。拠点回収も利用可能。 ・発泡スチロール製品もプラスチック回収の対象。 | ・一辺の長さが30cm以上のものは「粗大ごみ」。 ・ただし、粗大ごみ受付センターは「原則として粗大ごみではない」と回答しており、細かく砕いて一般ごみとして出すよう求めているとの情報もある。 | ・粗大ごみの扱いについて、公式案内と実運用に乖離がある可能性が示唆されている。迷った場合は細かくして資源として出すのが無難。 ・出典: 渋谷区公式ウェブサイト |
| 中野区 | 資源プラスチック | ・緩衝材や食品トレイは「資源プラスチック」。 ・軽くすすいで汚れを落とす。汚れが落ちないものは「燃やすごみ」。 ・中身の見える袋か、ふた付きの容器に入れる。 ・袋で出しにくいものは、1個につき10L相当の有料シールが必要な場合がある。 | ・一辺の長さが30cmを超えるものは「粗大ごみ」。 | ・令和6年4月からプラスチックの分別ルールが変更され、製品プラスチックも一括回収の対象となった。 ・出典: 中野区公式ウェブサイト |
| 杉並区 | プラスチック製容器包装 | ・発泡スチロールは「プラスチック製容器包装」として週1回回収。 ・中身の見える袋に入れて出す。 ・汚れの取れないものは「可燃ごみ」。 | ・最大辺がおおむね30cmを超えるものは「粗大ごみ」となる可能性がある。 | ・発泡スチロール緩衝材は「プラスチック製容器包装」に該当する。 ・出典: 杉並区公式ウェブサイト |
| 豊島区 | 資源(プラスチック) | ・発泡スチロール・緩衝材は「資源(プラスチック)」。 ・まとめて透明または半透明の袋に入れる。 ・プラマークを目安に分別することが推奨されている。 | ・区のウェブサイトに明確な記述なし。一般的な粗大ごみ基準(一辺30cm以上)が適用される可能性が高い。 | ・令和5年10月からプラスチックの資源回収が開始された。 ・出典: 豊島区公式ウェブサイト |
| 北区 | プラスチック | ・「プラスチックの日」に回収。 ・はさみやカッターで30cm以内に切断し、透明または半透明の袋に入れる。 ・汚れを水ですすぐなどして落とす。汚れが落ちない場合は「可燃ごみ」。 | ・一辺が30cmを超えるものは回収できないため、切断が必須。切断できない大きな製品は「粗大ごみ」。 | ・一部情報源では「可燃ごみ」とあるが、最新の公式情報では「プラスチック」であり、こちらが正しい。 ・出典: 北区公式ウェブサイト |
| 荒川区 | 燃やすごみ or 資源 (種類・状態による) | ・発泡スチロールの緩衝材などは「燃やすごみ」。 ・例外: 発泡スチロール製食品用トレイは「資源」としてネットで回収。 ・食品トレイは軽くすすいで出す。汚れが落ちないものは「燃やすごみ」。 | ・区のウェブサイトに明確な記述なし。大きなものは細かく砕いて「燃やすごみ」として出すことが推奨されている。 | ・緩衝材は「燃やすごみ」、食品トレイは「資源」と明確に分かれているのが特徴。 ・出典: 荒川区公式ウェブサイト |
| 板橋区 | 資源(プラスチック) | ・発泡スチロール・緩衝材は「資源」として回収。 ・汚れを拭き取るか水ですすいで落とす。汚れが落ちない場合は「可燃ごみ」。 ・透明・半透明の中身の見える袋に入れる。二重袋は不可。 | ・最大辺がおおむね30cm以上のものは「粗大ごみ」。 | ・令和6年10月からプラスチックの一括回収が開始された。 ・出典: 板橋区公式ウェブサイト |
| 練馬区 | 容器包装プラスチック | ・発泡スチロールの箱、緩衝材、トレイは「容器包装プラスチック」。 ・汚れがあるものはすすいで落とす。汚れやにおいが落ちないものは「可燃ごみ」。 ・ふた付きの容器または透明・半透明の袋に入れる。 | ・区のウェブサイトに明確な記述なし。一般的な粗大ごみ基準(一辺30cm以上)が適用される可能性が高い。 | ・区の処理施設では未成形の発泡スチロールを処理できないため、以前は「可燃ごみ」だったが、現在は資源として回収している。 ・出典: 練馬区公式ウェブサイト |
| 足立区 | プラスチック or 燃やすごみ | ・令和6年10月からプラスチックの一括回収が開始。発泡スチロールの容器・緩衝材は「プラスチック」として出す。 ・サッと「ひと洗い」または「ひと拭い」して汚れを落とす。 ・それ以前の情報では「燃やすごみ」とされていた。 | ・30cm角以上のものは「粗大ごみ」。 | ・分別ルールが最近変更されたため、古い情報に注意が必要。 ・出典: 足立区公式ウェブサイト |
| 葛飾区 | 資源 or プラマーク (種類による) | ・食品トレイ(発泡スチロール製)は「資源」の日に専用ネットへ出す。 ・緩衝材など、プラマークの付いた容器包装は「プラマーク」の日に出す。 ・いずれも軽くすすいで汚れを落とす。汚れが取れないものは「燃やすごみ」。 | ・高さ・幅・奥行のいずれかが30cmを超えるものは「粗大ごみ」。 | ・食品トレイと緩衝材で回収日が異なるのが特徴。食品トレイはプラマークが付いていても「資源」の日が優先される。 ・出典: 葛飾区公式ウェブサイト |
| 江戸川区 | 資源(容器包装プラスチック) or 燃やすごみ | ・商品の梱包や緩衝材として使われたもので、①プラマークがある、②銀色加工がない、③汚れていない、という3条件を満たすものは「資源」。 ・上記以外や、汚れがあるものは「燃やすごみ」。 ・資源として出す場合は、透明・半透明の袋にまとめて入れる。 | ・一辺が30cm以上のものは「粗大ごみ」。 | ・3つの条件をすべて満たす必要があるという、厳格なルールが特徴。 ・出典: 江戸川区公式ウェブサイト |
住民のための発泡スチロール処分・5つの黄金ルール
以上が東京23区の発泡スチロールの処分方法をまとめた表となります。情報量が多いため、全体像を掴むのは難しいかもしれません。このセクションでは、データを分析し、住民が日々の生活で実践できる、より分かりやすい指針と注意点を解説します。
ルール1:お住まいの区がどういったルールかを把握する
まず、自分の住む区が「資源ファースト」「焼却ファースト」「ハイブリッド」のどれに当たるかを確認しましょう。これがあなたの行動の基本方針を決定します。
- グループ1:資源ファースト区(例:千代田区、港区、新宿区など)
- 特徴:プラスチックリサイクルのインフラが比較的整っており、「きれいな発泡スチロールの梱包材は資源である」という考え方が基本です。迷った場合は、まず資源として出せるかどうかを検討するのが良いでしょう。
- グループ2:焼却ファースト区(例:世田谷区、文京区など)
- 特徴:発泡スチロールの多くを「燃やすごみ」として処理するのが基本方針です。基本は「燃やすごみ」と考え、例外品目(食品トレイなど)を確認する、という手順が効率的です。
- グループ3:ハイブリッド・複雑ルール区(例:江東区、葛飾区など)
- 特徴:単純な二元論では分けられない独自のルールを持っています。江東区の「つまようじテスト」のように、住民自身が素材の性質を見極める必要があったりします。これらの区に住む場合は、特に詳細なルールを注意深く確認する必要があります。
ルール2:迷ったら、砕いて袋へいれて捨てる
粗大ゴミ扱いとなるかどうかの境界線として、30cmという基準が、こちらの大きさに神経質になる必要はありません。大きな発泡スチロールは、指定のごみ袋に収まるサイズに小さく砕くことを第一に考えましょう。大田区が推奨するように、袋の中で作業すれば破片の飛散も防げます。これが最も現実的で価値のあるアプローチです。
ルール3:トレイは特別扱い
食品トレイは常に別のカテゴリーとして認識してください。まずスーパーの拠点回収ボックスの有無を確認し、なければ区の資源回収ルールに従いましょう。
ルール4:清潔さがリサイクルの鍵
簡単なすすぎや拭き取りで「食べ残しなし・べたつきなし・においなし」の状態にできなければ、それはリサイクルには向きません。迷わず「燃やすごみ」の袋に入れましょう。
ルール5:日付を確認する
東京のプラスチックリサイクルのルールは変化し続けています。年に一度は区の公式ごみ分別ページをブックマークから開き、ルールに変更がないか確認する習慣をつけましょう。
かさばる発泡スチロールを賢く小さくする方法
自治体のゴミ袋に入れるにも、大きすぎてそのままでは入らないのが発泡スチロールの厄介な点。ここでは、家庭で安全・簡単に小さくするための注意点と具体的な方法を解説します。
細かく分ける際は飛散に気をつける
緩衝材などに使われるブロック型の発泡スチロールは、そのままではゴミ袋をすぐに一杯にしてしまいます。大概の場合は手で割ったり折ったりして小さくすると思いますが、その際に粒状の破片がバラバラに散らばってしまうことがあります。
さらに、静電気を帯びやすいため、飛散した粒が衣服や床、壁などにくっついてしまい、掃除が非常に厄介になります。ゴミとして小さくする作業自体は簡単ですが、この「飛散」をいかに防ぐかが重要なポイントです。
方法①:手で割って小さくする
最も手軽な方法ですが、前述の通り飛散しやすいのが難点です。そこで、「大きめのゴミ袋の中で作業する」ことを強くおすすめします。
まず、発泡スチロールをゴミ袋の中に入れ、袋の口を片手でしっかり閉じます。そして、袋の上から力を加えて割ったり折ったりして更に小さくしていきます。こうすることで、飛散を袋の中に完全に封じ込め、後片付けの手間をなくすことができます。
方法②:スチールカッターで切り分ける
手作業による飛散をさらに防ぐのに有効なのが、スチールカッター(発泡スチロールカッター)です。これは熱で溶かして切断する道具で、100円ショップやホームセンターで手に入ります。
手で割るのとは異なり、粒状の結合を剥がすことなく分断できるため、細かなゴミの発生を最小限に留めることができます。手作業では難しい任意の大きさに、綺麗に裁断できるのもメリットです。ただし、カッターの刃は高温になるため、火傷や火災には十分注意して作業してください。
【絶対にNG!】自力での焼却処理はおこなわないでください
発泡スチロールは燃えるゴミではありますが、だからといって「燃やしてしまえば良い」と考え、ご家庭の庭などで自力で焼却処分をするのは絶対にやめましょう。
専門の焼却炉であればクリーンに処理できますが、家庭で燃やすと不完全燃焼を起こし、黒いススや一酸化炭素などの有害物質が発生します。体調不良を引き起こす危険があるだけでなく、廃棄物処理法で禁止されている行為であり、罰則の対象にもなり得ます。必ずルールに従って処分してください。
あなたに最適な処分方法は?7つの捨て方を徹底比較
ここまでご紹介した7つの方法を、あなたの「目的」に合わせて整理しました。この比較表を見れば、どの方法が今のあなたに最も合っているかが一目で分かります。
| 悩み・目的 | 最適な方法 | 詳細 | 注意点 |
| とにかく無料で捨てたい | ①自治体の普通ゴミ | 普段通りのゴミ捨てが可能。分別ルールさえ守れば費用はかからない。 | 自治体のルール(分別、サイズ、出す日)を正確に確認する必要がある。 |
| 資源リサイクルに貢献したい | ③資源回収ボックス | スーパー等に持ち込むだけで、手軽にサステナブルな活動に貢献できる。 | 回収は基本的に食品トレイのみ。洗浄・乾燥が必須。 |
| まだ使えるから捨てるのはもったいない | ⑤緩衝材/⑥断熱材として再利用 | 梱包材や省エネグッズとして活用できる。処分費用がゼロになる。 | 保管場所に余裕があることが前提。汚れたものは不向き。 |
| まとめて・たくさん・楽に捨てたい | ⑦不用品回収業者 | どんな不用品もまとめて、分別・梱包・搬出まで全て任せられる。 | 費用がかかる。業者によって料金が異なるため、見積もりを取ると安心。 |
上記を見ても分かる通り、よほど一度に大量のゴミが出ない限りは、ご自身で工夫して処分することも可能です。しかし、少しでも「面倒だ」「時間がない」と感じる場合は、専門の業者を頼るのが最も効率的です。
手間と時間をかけたくないなら不用品回収業者が最適
大量の発泡スチロールや、他の不用品もまとめて処分したいなら、不用品回収業者に依頼するのが最も簡単でスピーディな解決策です。
業者を利用するメリットは以下の通りです。
- 面倒な分別・洗浄・解体が一切不要!
一番のメリットは、手間が全くかからないことです。汚れた食品トレイも、大きな緩衝材も、そのままの状態でOK。すべてスタッフが責任を持って分別・梱包・搬出します。 - 自分の都合の良い日時に回収に来てくれる!
自治体のゴミ出しのように朝早く出す必要はありません。土日祝日や、最短で依頼したその日のうちに回収に来てくれる業者も多く、あなたのスケジュールに柔軟に合わせられます。 - 発泡スチロール以外の不用品もまとめて処分できる!
大掃除や引越しで出た家具・家電・衣類・布団など、どんな不用品も一緒に回収してもらえます。トラックに積める分であれば定額、というお得なパック料金を用意している業者も多く、結果的にコストを抑えられる場合もあります。
発泡スチロールってどんなもの?
日々の生活の中でも割と馴染み深い発泡スチロールですが、その種類や形状は様々で大きく分けて3種類に分かれます。
| 用途 | 区分 | 特徴 |
| 一般的な発泡スチロール | expanded polystyrene (EPS) | 梱包などに使用される |
| 食品トレイ系の発泡スチロール | polystyrene paper (PSP) | お肉や魚などのトレイ |
| 断熱材系の発泡スチロール | extruded polystyrene (XPS) | 薄い板状のもの 色が付いている場合あり |
これらは全てポリスチレンというプラスチックを「発泡」させたものですが、製法が違うため、固さや特徴が異なります。
共通する素材の特徴として、非常に軽く、衝撃に強く、浮力があり水を弾くという点が挙げられます。その一方で、自然に分解されることはないため、環境への影響を考慮し、処分の際にはしっかりと集めて正しく捨てることが求められます。
発泡スチロールの種類について
発泡スチロールは大きく分けて3つの種類に分けられます。
種類ごとに推奨される捨て方や使用方法が異なりますので、捨てたい発泡スチロールがどの種類にあたるのか確認をしてみてください。
1. ビーズ法発泡スチロール

名前の通り1つ1つがビーズの形をしており、ビーズを複数繋げて箱型にし、魚介類の輸出用箱などに使われています。『expanded polystyrene』を略してEPSとも呼称されています。
軽くて衝撃吸収性に優れており、固められたビーズ法発泡スチロールは家具家電の緩衝材に使われることも多いです。ビーズを固めず一か所に集めることによりフワフワとして感触となり、クッションの中身にも使われています。
普通ゴミとして捨てることができるのはもちろん、使い方によっては再利用にも適しているので緩衝材やクッション材として活用することも可能です。
昨今では、ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)は燃えにくく、燃焼した際に生じる有毒物質も極めて低くなっています。地中環境にやさしい素材で作られるなどデメリットも少なくなっています。
2. 発泡スチレンシート

発泡スチレンシートは発泡スチロールトレイ(トレー)とも呼ばれ、『polystyrene paper』を略してPSPとも呼称されます。ビーズ法発砲スチロールと比べると、発泡率が低く少し固めです。
液体や臭いを通しにくいという特徴も持っているので、肉や魚などを載せる時に使われる容器として使われています。食品を載せるトレイ以外にもカップラーメンの容器などにも使われています。
発泡スチレンシートは普通ゴミとして捨てることも可能ですが、スーパーに設置されている資源回収ボックスを利用してリサイクルに貢献することもできます。
ただし、汚れたままの状態ではリサイクルに不向きです。回収ボックスを利用する時は、発泡スチレンシートの汚れをしっかりと洗い流し、乾燥をさせてから投入するようにしましょう。
3. 押出法発泡ポリスチレン

ポリスチレンを押出機から押し出して、板状にした発泡スチロールです。『extruded polystyrene』を略してXPSとも呼称されます。
戸建てやマンションの断熱材や、畳の芯材、断熱材などに使われています。軽量で薄いものの断熱性が高く、水や湿気にも強いです。住宅やマンションの耐荷重を圧迫することなく快適な空間を作り出せる便利な発泡スチロールです。
こちらは割合サイズが大きいため、ゴミとして捨てる際は粗大ごみ回収を利用するか、細かく切断して普通ゴミに出す必要があります。
素材と特徴
発泡スチロール自体は、小さなビーズ粒からできておりその粒を重ね合わせくっつけて、箱やトレイなどが作られています。
基本的に非常に軽く、衝撃に強い性質を持っています。また、浮力があり水をはじきます。しかし、部分的な強度はそこまで高くはなく、道具がなくても人の手で砕くことができます。
自然に放置していても分解するようなことはなく、処分の際にはしっかりと集めて捨てることが必要です。放置されてしまうと自然環境に影響を与えるような懸念もあるでしょう。
原材料は石油から作られるポリエチレンビーズです。石油から作られるプラスチック製品の約1%が発泡スチロール製品となっています。
発泡ってどういう意味?
発泡スチロールの「発泡」とは、製造過程において原料となる小さなプラスチック粒(ポリスチレンビーズ)にガスを含ませ、蒸気で加熱することで、空気の気泡によって体積を大きく膨らませることを意味します。
驚くべきことに、製品となった発泡スチロールの体積は、約98%が空気で、原料である石油由来の樹脂はわずか2%しかありません。少ない資源で軽量かつ大きな容器をつくれる、非常に効率的で環境に優しい製品といえるのです。
発泡スチロールの体積は、2%が石油、残りの98%が空気で作られています。石油を使用しているものではありますが、少ない資源で環境にも優しい製品といえます。
捨てるのが大変?
身近なものでは緩衝材として商品と一緒に梱包されていることが多く、目的を果たしてしまうとただのゴミとなってしまうことがほとんどです。
板状の発泡スチロールをそのまま再活用するような場合を除いて、加工などをして何かに使ったりすることには適しておらず、割ったり砕いたりすることで発泡スチロールの粒が飛散してしまうなど、扱いには注意が必要です。
また、飛散した場合、静電気などによって衣服や物などにくっつきやすい性質もあるため、掃除をするのも厄介です。ゴミとして小さくして処分するような場合を除いて、割ったり砕いたりするのは適していないでしょう。

捨てる際は割ってからゴミ袋に入れるのではなく、袋に入れた状態で袋の中で割るのが最適でしょう。
何ゴミで処分できる?
基本的に発泡スチロールは自治体のゴミ回収で処分することができます。
ただし、自治体によって発泡スチロールの分類や扱いが異なるため、注意が必要です。
一部自治体の例を見てみましょう。
※以下の表に記載されている分別に関しては、プラマークが有る製品が対象となります。
プラマークの無い製品については各自治体のホームページやゴミごとの捨て方をご確認ください。
| 自治体 | 分類・品目 | 注意点 |
| 東京都 渋谷区 | 資源ゴミ 粗大ゴミ | 一辺が30cm未満 一辺が30cmを超える場合 |
| 東京都 港区 | 資源プラスチック | 30cmを超えても回収 |
| 神奈川県 川崎市 | プラスチック製容器包装 普通ゴミ(購入物) 粗大ゴミ(購入物) | – 一辺が50cm未満 一辺が50cm以上を超える場合 |
| 神奈川県 横浜市 | プラスチック製容器包装 | プラマークがなくても 多くのものが対象 |
| 埼玉県 さいたま市 | 可燃ゴミ | カップ面の容器なども同様 |
| 埼玉県 新座市 | 可燃ゴミ | 家電製品に付属する緩衝材は 販売店での処分推奨 |
| 千葉県 千葉市 | 可燃ゴミ | 指定の袋に入れて捨てる |
| 千葉県 習志野市 | 可燃ゴミ | – |
| 茨城県 水戸市 | プラスチック製容器包装 | 汚れている場合は可燃ゴミ 白色トレイは「資源物B」 |
上記のように、自治体により分類が細かく異なります。
また、プラマークの有無でも処分方法が異なってきます。自治体によっても異なりますが、プラマークのある発泡スチロールは資源ゴミとして扱われる場合があります。
その点も踏まえて、分別方法をしっかりと頭に入れて捨てる必要があるでしょう。
容器包装リサイクル法とは?
平成9年4月から本格施行されたこの法律は、一般の家庭からゴミとして排出される「容器」や「包装」(びん、PETボトル、紙箱、レジ袋など)を、単なるゴミではなく資源としてリサイクルすることを目的としています。
この法律により、私たち消費者は「正しく分別して排出する」、自治体は「分別収集を行う」、事業者は「リサイクル(再商品化)する」という役割分担が定められました。スーパーの店頭などで回収される発泡スチロール製トレイも、この法律に則ってリサイクルされています。
6.4. 歴史やその他のリサイクル用途
発泡スチロールは、1950年にドイツで開発され、50年以上の歴史があります。それ以前は、緩衝材としてコルクが使われていましたが、効果が似ていることから、その代用品として広く世界に普及しました。
リサイクルされた発泡スチロールは、再び発泡スチロール製品に生まれ変わるだけでなく、ハンガーやおもちゃ、ボールペンといったプラスチック製品の原料になったり、専門の処理施設で油化還元されたり、発電の燃料として利用されたりと、様々な用途で再利用されています。
いらなくなった発砲スチロールを捨てるなら『お助けうさぎ』におまかせ!
今回は発泡スチロールの捨て方についてご紹介いたしました。
発泡スチロールは基本的に普通ゴミとして捨てることができるので、自力での処分に困ることはあまりありません。自治体の分別ルールに従い、発砲スチロールを捨てていきましょう。
もし、サイズの大きい発砲スチロールを捨てたいと思った時や、大量の発泡スチロールを捨てたいと不便を感じた時はお助けうさぎの不用品回収サービスをご利用ください。
お助けうさぎは東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城を中心に不用品回収サービスをおこなっている会社です。ありとあらゆる不用品を回収しています。
発砲スチロールの他にも、粗大ゴミ回収・ゴミ屋敷清掃・遺品整理などあらゆるニーズにお応えすることが可能です。
お助けうさぎの料金は分かりやすい定額パックをご用意しています。一番お得に処分できる金額でご提示いたしますので、余計な費用が掛かってしまうこともありません。
お問い合わせは24時間365日いつでも受け付けておりますので、まずはお見積もりだけという方もぜひお気軽にご相談ください。ご相談とお見積もりは無料で承っております。
▼どんな不用品でも格安回収!▼
【お助けうさぎの料金プランはこちら】