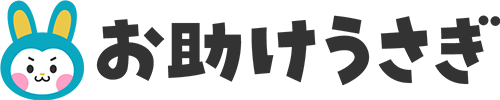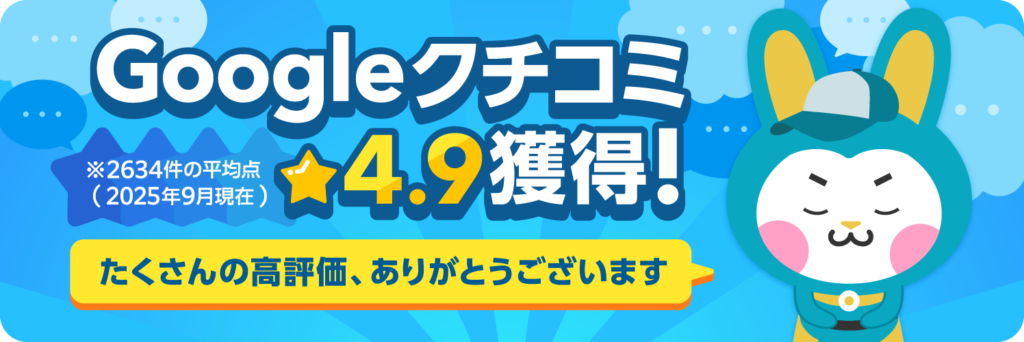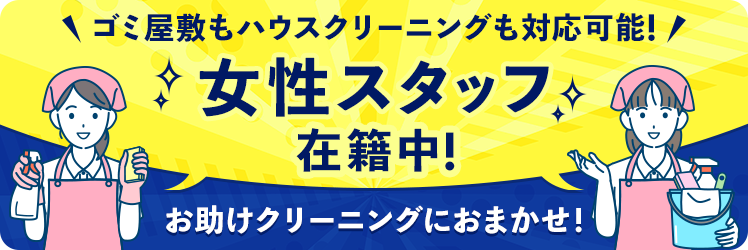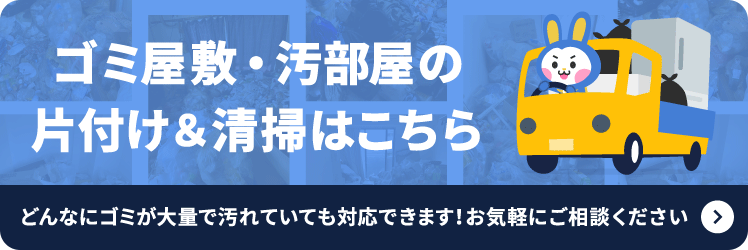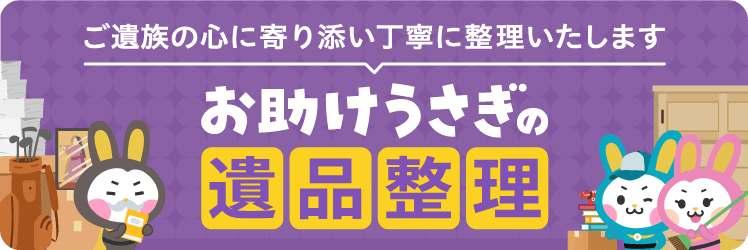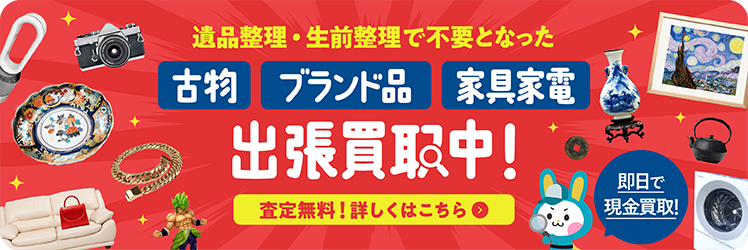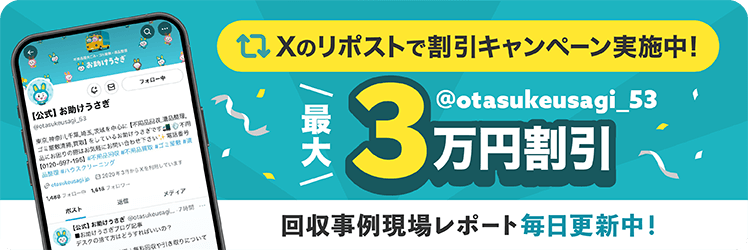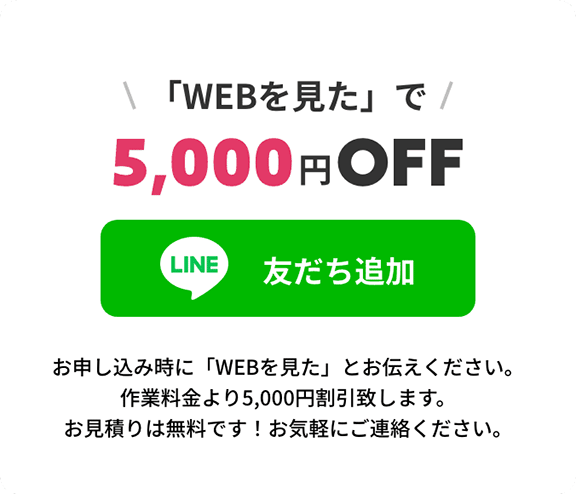お守りの返納方法は?|捨て方や処分方法を解説
不用品別の処分方法年末の大掃除で、昔いただいたお守りが出てきた。願いが叶ったので感謝を込めてお返ししたいけど、作法がわからない――。
大切なお守りだからこそ、どう手放すべきか迷いますよね。「処分」という言葉を使うのも、何だか気が引けるものです。
ご安心ください。この記事では、「お守りの返納方法」や「お守りの捨て方」に関するあらゆる疑問に、不用品回収のプロの視点も交えてお答えします。
内容につきましては「正しい返納方法」「タイミング」「神社とお寺の違い」「費用」「注意点」はもちろん、「郵送の具体的な手順」や「人形など一緒に返納できるもの」まで、全てを網羅しております。
あなたにぴったりの、感謝が伝わる手放し方が必ず見つかります。ぜひご参考ください。
【お守りと一緒に、ご自宅の不用品もまとめてスッキリしませんか?】
\今だけ!春のWEB割で5,000円OFF/
詳細はバナーをタップしてお問合せください↓↓
なぜ返納するの?知っておきたいお守りの意味と基礎知識
お守りを手放す方法を知る前に、まずはお守りがどのような存在で、なぜ返納するのが良いとされるのかを知っておきましょう。その背景を理解することで、より感謝の気持ちを込めてお返しすることができます。
お守りは神様の力が宿る「分身」
お守りは、単なる縁起物ではありません。神社やお寺でいただいたお守りは、神様や仏様のご分霊(わけみたま)が宿った、いわば神様の「分身」です。常に身につけたり、身近な場所に置いたりすることで、災いから私たちを守り、願いが叶うように力を貸してくださる神聖なものと考えられています。
お神札(おふだ)との違いは?
お守りとお神札は、どちらも神様の力が宿る大切なものですが、役割が少し異なります。お神札が主に神棚など家の中にお祀りし、家全体を守っていただくものであるのに対し、お守りは小型化され、個人が常に身につけて持ち歩けるようにしたものです。
古いお守りを持ち続けるのはNG?神道に伝わる「常若(とこわか)」の考え方
神道には「常若(とこわか)」という大切な考え方があります。これは「常に若々しく、生命力に満ち溢れた状態でいること」を尊ぶ思想です。伊勢神宮が20年に一度社殿を建て替える「式年遷宮」もこの思想に基づいています。
お守りも同様に、1年経つと力が弱まったり、持ち主の厄を吸ってくれたりしていると考えられます。そのため、1年ごとにお返しして新しいお守りを授かり、常にみずみずしい神様のご加護をいただくのが良いとされているのです。
「購入」「処分」はNG?「授かる」「返納する」が正しい言葉遣い
神様の力が宿るお守りは、モノを売買する感覚とは異なります。お金を払う場合でも、それは対価ではなく神様への感謝の気持ち(初穂料・お布施)です。そのため、「お守りを買う」ではなく「授かる(さずかる)」や「受ける」と言います。
同様に、手放す際も「捨てる」「処分する」ではなく、神様にお返しするという意味で「返納(へんのう)する」や「お納めする」と表現するのが適切です。
返納・処分のタイミングはいつ?【3つの時期】
では、お守りはいつ手放すのが良いのでしょうか。主に3つのタイミングが考えられます。
① 授かってから「1年」が一般的な目安
最も一般的なのが、授かってから1年が経過したタイミングです。初詣で新しいお守りを授かる際に、前年のお守りを感謝とともに返納するというのが古くからの慣習です。
② 合格祈願・安産祈願などは「願いが叶った時」
合格祈願や安産祈願、縁結びなど、特定の目的があるお守りは、その願いが成就したときが返納の絶好のタイミングです。1年を待たずとも、願いが叶ったことを神様・仏様に報告し、感謝を伝えてお返ししましょう。これを「お礼参り」といいます。
③ 思い入れがあって手放せない…記念に持ち続けても良い?
無事に子どもが生まれた安産祈願のお守りなど、記念として手元に置いておきたい場合もあるでしょう。古いお守りを持ち続けてもバチが当たるわけではありませんので、ご安心ください。
ただし、神聖なものですから、引き出しの奥にしまい込むのではなく、神棚や目線より高い清潔な場所に飾り、時々お礼参りをするなどして、感謝の気持ちを持ち続けることが大切です。
古いお守りの返納・処分方法7選|費用・手間で徹底比較
お守りを手放す方法は一つではありません。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選べるように、7つの選択肢を比較しながら詳しく解説します。
| 返納・処分方法 | 推奨度 | 費用の目安 | 手間 | こんな人におすすめ |
| ① 授かった寺社へ返納 | ★★★★★ | 無料〜お気持ち | △ | 最も丁寧に返したい人 |
| ② 近くの寺社へ返納 | ★★★★☆ | 無料〜お気持ち | 〇 | 授かった場所が遠い人 |
| ③ 郵送で返納 | ★★★★☆ | 送料+お気持ち | 〇 | 遠方で多忙な人 |
| ④ どんど焼き | ★★★☆☆ | 無料〜数百円 | △ | 正月のタイミングで手放したい人 |
| ⑤ お焚き上げ代行サービス | ★★★☆☆ | 2,000円〜 | ◎ | 手間をかけたくない人 |
| ⑥ 自宅で供養し処分 | ★★☆☆☆ | 数円(塩代) | 〇 | どうしても手段がない場合の最終手段 |
| ⑦ 不用品回収業者 | ★☆☆☆☆ | 業者による | ◎ | 他の不用品とまとめて処分したい人 |
方法①:授かった神社・お寺に返納する
最も丁寧で正式な方法は、お守りを授かった神社やお寺に直接お返しすることです。
多くの寺社の境内には「古札納所(こさつおさめしょ)」や「お守り納め所」という箱や場所が設置されていますので、そちらにお納めしましょう。見当たらない場合は、社務所や寺務所の職員の方に直接お渡しすれば問題ありません。年末年始は特設の納め所が設けられていることも多いです。
方法②:近くの神社・お寺に返納する
旅行先で授かったお守りなど、直接お返しするのが難しい場合は、近所の神社やお寺に返納しても問題ありません。
ただし、いきなり古札納所に入れるのではなく、一度社務所・寺務所の方に「遠方で授かったお守りなのですが、こちらでお納めしてもよろしいでしょうか」と一声かけるのがマナーです。快く引き受けてくださる場合がほとんどですが、寺社によっては自分たちのところで授与したものしか受け付けない方針の場合もあるため、事前の確認は大切です。
方法③:郵送で返納を受け付けている寺社に送る
遠方で直接行けない、行く時間がないという方には郵送での返納が便利です。ただし、すべての寺社が対応しているわけではありません。
【手順1】まずは寺社の公式サイトで郵送対応の可否を確認
公式サイトに「お守りの郵送返納について」といった記載がないか確認します。見つからなければ電話で問い合わせましょう。いきなり送りつけるのは絶対にやめましょう。
【手順2】現金書留でお納め料(お焚き上げ料)とメモを同封
返送する際は、お守り本体だけでなく、感謝の気持ちとしてお焚き上げ料(お気持ちで結構です)と、内容を記したメモ(「お守りのお焚き上げをお願いいたします」など)を添えるのが丁寧です。お焚き上げ料は現金書留で送るのがマナーです。
【手順3】お守りを白い紙に包んで送る
お守りを裸で封筒に入れるのではなく、まず白い半紙や和紙できれいに包んでから、封筒に入れて送りましょう。
方法④:どんど焼き・左義長(さぎちょう)でお焚き上げする
どんど焼き(左義長とも呼ばれます)は、小正月(1月15日前後)に、お正月の松飾りやしめ縄、古いお守りなどを集めて燃やす火祭りの神事です。地域の神社や広場で行われます。
お守りもこのどんど焼きでお焚き上げをしてもらえますが、地域によっては正月飾りしか受け付けない場合もあるため、事前に確認しておくと確実です。
方法⑤:お焚き上げ代行サービスを利用する
最近では、オンラインで申し込み、お守りをキットに入れて郵送すると、提携先の神社できちんとお焚き上げをしてくれるサービスもあります。
「忙しくて時間がない」「近くに返納できる場所がない」という場合に便利な選択肢です。費用はかかりますが、供養証明書を発行してくれるサービスもあり、安心して任せることができます。
方法⑥:自宅で供養してから処分する
神社やお寺にどうしても返納できず、すぐに手放したい場合の最終手段として、自宅で供養してから処分する方法があります。
- 白い半紙や和紙を広げ、その上にお守りを置きます。
- 感謝の気持ちを込め、お守りの上に塩をひとつまみかけます。(左→右→左の順にかけるとより丁寧です)
- そのまま白い紙で丁寧に包みます。
- ここまで行うと「神様の力が宿るもの」から「物」になったと考えられ、自治体のルールに従って可燃ゴミとして出すことができます。
これはあくまでやむを得ない場合の手段と考え、可能な限り神社やお寺にお返しするのが望ましいでしょう。
方法⑦:不用品回収業者に回収を依頼する
大掃除や遺品整理などで、お守り以外にも処分したい家具や家電などが大量にある場合は、不用品回収業者にまとめて依頼するのも一つの手です。
- メリット: 面倒な分別が不要/他の家具・家電も一括で処分できる/最短即日で対応可能
- 注意点
- お守り単品での回収は承っておりませんが、他の不用品とご一緒の場合、お客様に代わってルールに則り適正に処理いたします。
「他の物も一気に処分したい」「処分に手間をかけられない」という場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
【マナーと注意点】感謝を伝えるための10の作法
お守りを手放す際は、失礼にあたらないよう以下の点に注意しましょう。
① 神社とお寺を間違えない(最も重要な注意点)
神社で授かったお守りは神社へ、お寺で授かったお守りはお寺へ返納するのが大原則です。神様と仏様は異なりますので、間違えないようにしましょう。
② お納め料(お焚き上げ料)を添えるのが丁寧
返納は無料で受け付けてくれるところがほとんどですが、感謝の気持ちとしてお賽銭を入れたり、お焚き上げ料をいくらかお納めしたりするのが丁寧な作法です。
③ お守りと一緒に返納・処分できるもの、できないもの
- OKなもの: お札、熊手、破魔矢、おみくじなど、同じ寺社で授かった縁起物。
- 要確認なもの: だるま、神棚、人形、ぬいぐるみ。これらは専門の供養(人形供養など)が必要な場合が多く、寺社によって対応が異なります。必ず事前に確認しましょう。
- NGなもの: 仏具(お寺の専門家へ)、家庭ごみ、電池などの危険物。
④ 金属・プラスチックなど燃えない素材のお守りの扱い方
キーホルダータイプなど燃えない素材が使われているお守りは、お焚き上げができません。授かった寺社に相談するのが一番ですが、難しい場合は分別して不燃ゴミとして出すか、不用品回収業者にご相談ください。
⑤ 返納する日は大安が良い?六曜は気にしなくてOK
神社の行事は仏教由来の六曜(大安、仏滅など)とは関係がないため、気にする必要はありません。ご自身の都合の良い日で大丈夫です。
⑥ 代理の人が返納しても問題ない?
ご本人が行けない場合、ご家族やご友人に代理で返納をお願いしても全く問題ありません。大切なのは感謝の気持ちです。
⑦ お守りの中身は絶対に開けない
お守りの袋の中には、神様の力が込められた内符が入っています。中身を見ることは神様に対して失礼にあたり、ご利益がなくなるとも言われています。興味本位で開けるのはやめましょう。
⑧ 他人にお守りを譲渡しない
ご利益があったからといって、古いお守りを「幸せのおすそ分け」として他人に譲るのはNGです。お守りは授かったその人のためのものです。
⑨ 必ず感謝の気持ちを伝える
どんな方法を選ぶにせよ、一番大切なのは「一年間お守りいただき、ありがとうございました」という感謝の気持ちです。手を合わせ、心の中でしっかりとお礼を伝えましょう。
⑩ ゴミとして捨てるのは避ける
前述の自宅で供養する方法もありますが、神様の分身を他のゴミと一緒にゴミ袋に入れることに抵抗を感じる方も多いはずです。できる限り神社やお寺にお返ししましょう。
これでスッキリ!お守りの返納・処分に関するよくある質問(Q&A)
Q. 違う神社に返納するのは、本当に失礼じゃないですか?
A. 基本的には問題ありません。神様同士は協力し合うと考えられており、多くの神社では快く受け入れてくれます。ただし、感謝の気持ちを伝え、一言断りを入れるのが丁寧な対応です。
Q. 旅行先で授かったお守りはどうすればいいですか?
A. 一番良いのは次にその地を訪れた際にお礼参りを兼ねて返納することですが、難しい場合は「近くの神社へ返納」または「郵送での返納」がおすすめです。
Q. どこの神社で授かったか忘れてしまいました…。
A. その場合は、お近くの大きな神社(地域の「総鎮守」など)に相談してみるのが良いでしょう。多くの神社を受け入れている「古神札納め所」に納めるのも手です。
Q. 郵送で送る際、封筒の宛名書きはどうすればいいですか?
A. 神社の正式名称を書き、「社務所 御中」または「お焚き上げ受付 御中」と記載するのが一般的です。
Q. 返納後、新しいお守りはすぐに授かった方がいいですか?
A. 返納と同時に新しいお守りを授かるのがスムーズですが、必ずしも同日である必要はありません。ご自身の良いタイミングで、新たな気持ちで授かりましょう。
自分に合った方法で感謝を込めてお守りを返納しましょう
この記事では、お守りの返納・処分に関する7つの方法と、知っておくべき作法や注意点を詳しく解説しました。
基本は「授かった寺社に感謝を込めて返納する」ことですが、難しい場合は郵送や近くの寺社にお願いするなど、ご自身の状況に合った方法を選んでみてください。一番大切なのは、これまで見守ってくれたことへの感謝の気持ちです。
そして、お守りの整理をきっかけに、お部屋全体の片付けや不用品の処分を進めたいとお考えでしたら、私たち「お助けうさぎ」が力になります。家具や家電など、処分に困るものをまとめて回収いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。