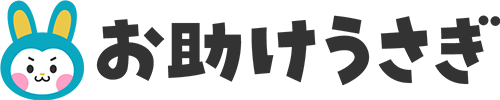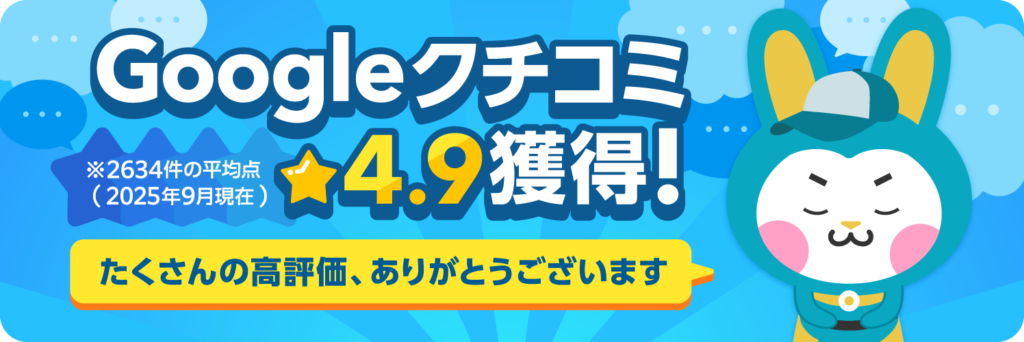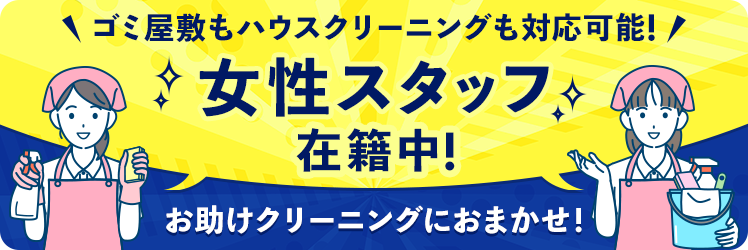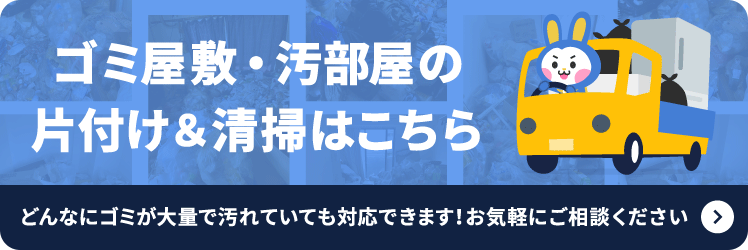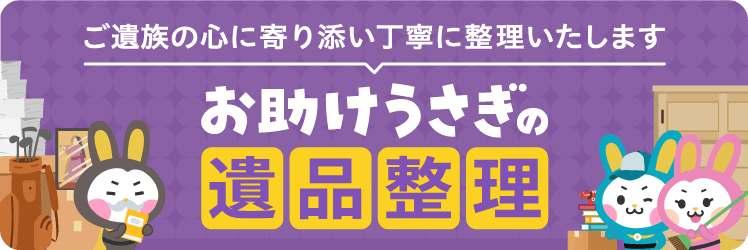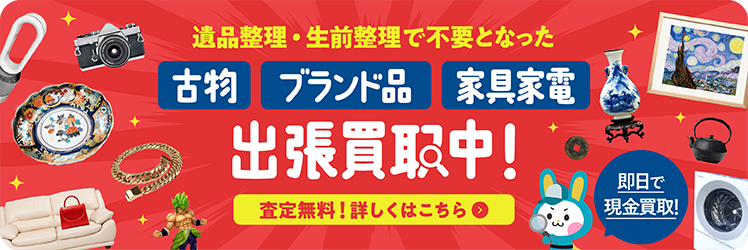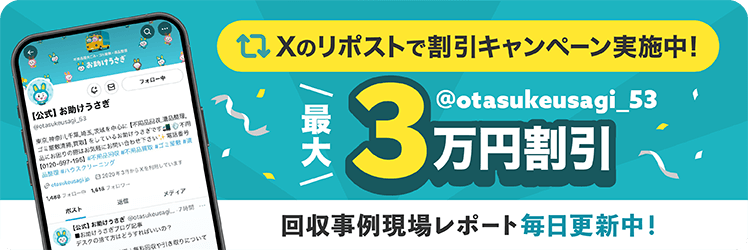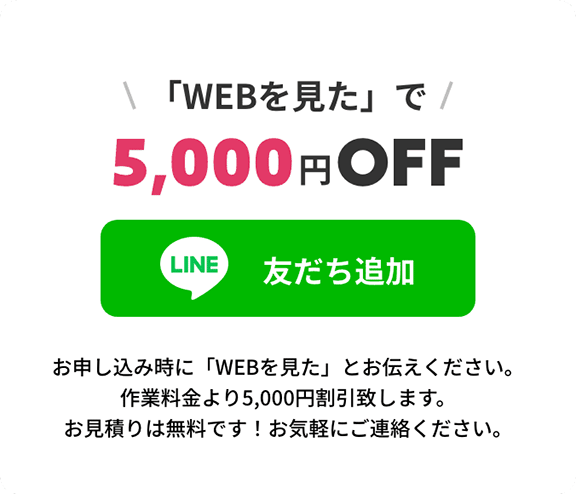【専門家監修】土の捨て方7選|無料回収や引き取りについて詳しく解説
不用品別の処分方法以前はきれい好きだった親の家が、帰省するたびに物が増え、少しずつ散らかっていく。その変化を見るたびに、強い違和感が胸に広がります。
片付けを提案しても、「これはまだ使う」「捨てないで」と感情的に拒否されてしまう―。
その光景を目の当たりにして、「もしかして認知症の始まりなのでは…?」と言葉にできない不安や焦りが胸に重くのしかかります。
厚生労働省の調査によると、65歳以上の約7人に1人が認知症を発症していると推計されています。そして、その中核症状である判断力や記憶力の低下は、片付けやゴミ出しができなくなる原因の一つとされています。
この記事では、親が片付けられなくなる主な原因や、家族が今日から実践できる具体的な対策、専門業者に頼る際のメリットと心理的ハードルの乗り越え方、信頼できる業者の見極め方までを、分かりやすく解説します。
この記事を読むと以下のことが分かります。
・親が片付けられなくなる主な原因
・家族が今日からできる具体的な対策
・業者に頼ることが「親不孝ではない」理由とメリット
・信頼できる片付け業者の見分け方
「もしかして認知症…?」親が片付けられないのは、あなたのせいではありません
「もっと頻繁に実家に顔を出していれば…」
「なぜ気づいてあげられなかったのか」
そのように自分を責めてしまっていませんか。
忙しい毎日のなかで、帰省するたびに散らかっていく実家を目の当たりにすれば、強い不安や罪悪感、そして「このままでは危ないのでは」という焦りに押しつぶされそうになるのも、決して不思議なことではありません。
しかし、親が片付けられなくなるのは、あなたの努力不足ではありません。
加齢や認知機能の変化・体力の衰え・さらには孤独や心理的不安など、複数の要因が重なって、誰にでも起こりうることです。
そして知っておいてほしいのは、こうした問題は一人で抱え込む必要はないということ。
支援してくれる公的機関や、専門知識を持つ片付け業者が存在し、親の安全や尊厳を守りながら解決へと導く方法もあります。
この記事では、その第一歩として原因と対策を整理し、無理なく前向きに進めるための具体的な方法をご紹介します。
なぜ?認知症で片付けられなくなる3つの主な原因
「片付けができない」という一見単純な行動の変化にも、いくつかの背景が関わっています。
認知症の場合、その要因は大きく3つに分けられます。
認知症で片付けられなくなる3つの主な原因
・脳の働きの変化による認知機能の低下
・気持ちや心理状態の揺らぎから生まれる不安や執着
・年齢とともに現れる身体機能の衰え
これらが単独、あるいは組み合わさって起こることで、日常の片付けが難しくなります。ここでは、それぞれの原因について順を追って解説します。
原因1:認知機能の低下(忘れる・手順がわからない)
片付けという行動は、一見単純に思えても、実はさまざまな力が組み合わさって成り立っています。
片付けに使う力
1. 物の位置や必要性などを判断する(判断力・記憶力)
2. どう片付けるか手順を組み立てる(計画力・遂行機能・注意力)
3. 整理を実行する(体力・バランス力・可動域)
認知症になると、この流れを支える判断力や記憶力、段取りを組み立てて実行する力が低下し、途中で目的や手順を見失いやすくなります。注意の持続や切り替えも難しくなり、始めた作業が中断されたままになることも少なくありません。
また、視空間認知の変化により「物の定位置」が思い出せず、とりあえず置いたものをそのまま忘れてしまう「仮置き」も増えていきます。その結果、片付けが途中で止まる、同じ物を何度も買ってしまう、物を出しっぱなしのまま放置するといった行動が見られるようになります。
このように、認知症による片付けの困難は脳の働きの変化によるものです。叱ったり説得するのではなく、片付けのハードルを下げる工夫(物の置き場所を見える化する・動作を簡略化するなど)といった環境の工夫が有効です。
さらに次に説明する「心理的な不安」も、片付けられなくなる大きな要因の一つです。
原因2:心理的な不安(物を捨てられない・現状維持バイアス)
認知症の方が片付けられなくなる背景には、心理的な要因も大きく影響します。
記憶の曖昧さが不安を生み、「いつか必要になるかも」という気持ちが強くなります。大切なものを手放す痛み(損失回避)や、慣れた状態を変えたくない心理(現状維持バイアス)が働くため、物を減らすという決断自体が難しくなってしまいます。
また孤独感や喪失体験があると、モノが心の支えや生活を守る「証」となり、ますます手放せなくなります。そうした心理から、とりあえず取っておく物が積み重なり、家が次第にゴミ屋敷のようになっていきます。
こうした心理的な背景を理解せずに「捨てよう」「片付けなきゃ」と正論で押しつけてしまうと、強い不安や怒りが表れ、反発や拒絶を招くことも少なくありません。
大切なのは安心を先に示すことです。写真に残す、一時保管用の箱を用意する、あとで戻せる仕組みをつくるなどの工夫が、不安を和らげるのに有効です。
ただし、心理的な要因だけでなく、体力や身体機能の変化も片付けを難しくする大きな要因のひとつにもなります。
原因3:身体的な問題(体力低下・億劫になる)
片付けの難しさは、認知症による記憶や判断だけでなく、身体的な変化からも生じます。
関節痛・筋力の低下・視力の変化・めまいなど、小さな不調の積み重ねが基本的な片付けの動作を妨げます。その結果、通路が狭くなる → 動きにくい → さらに片付けが億劫になる、という悪循環に陥ります。
よく見られる状況としては次のようなケースです。
身体的な問題でよく見られる状況
・よく使う物が床や椅子の上に滞留する
・電源コードや敷物に足を引っかけやすくなる
・収納が使われなくなり、物が出しっぱなしになる
・横になる・座る時間が長くなり作業ができない
ここで大切なのは、「見た目のきれいさ」よりも安全性を優先することです。収納の高さを腰から胸のあたりにそろえる、通路幅を確保するなど、これだけでも転倒や火災、不衛生な環境のリスクを大きく減らせます。
なお、片付けの困難は認知症に限らず、うつ病、薬の副作用、視覚・聴覚の変化、慢性痛などでも起こり得ます。変化が気になるときは、医療機関や地域包括支援センターに相談し、原因を一緒に確認することが大切です。
家族が今日からできる!親子関係を壊さないための4ステップ対策
認知症の可能性がある片付けの困難は、家族の声かけ次第で、大きく状況が変わることもあります。大切なのは「片付けさせること」ではなく、親の安全と気持ちを守りながら無理なく行動につなげる工夫です。
ここでは、今日から無理なく実践できる具体策を、感情面への配慮(情緒的アプローチ)にも触れつつ、わかりやすく解説します。
どれも特別な知識や道具がなくても取り入れられる方法ですので、できるところから試してみてください。
ステップ1:まず安全確保から。片付けより「動線づくり」を優先する
片付けの最初の目的は、部屋をきれいに見せることではありません。最も大切なのは「転ばない・火事を起こさない」という最低限の安全を確保することです。見た目を整えるのは後回しにして、まずは「安全に動ける道」をつくりましょう。
片付けの優先順位は、次のように考えるとスムーズです。
片付けの優先順位
1. 危険の回避(転倒・火の元)
2. 衛生の改善
3. 利便性の向上
4. 見た目を整えること
初日は長時間かけて片付ける必要はありません。次のような、15分程度の安全チェックだけでも十分です。玄関 → トイレ → 台所の順に見ていくだけでも、暮らしやすさは大きく変わります。
15分程度の安全チェック
・通路幅を60cm以上確保し、ドア前や廊下、トイレ前を塞がない
・コンロやヒーターの1m圏内にある紙や布、スプレー缶を一時退避する
・電源コードは束ねて固定し、緩んだマットは撤去する
・夜間に使う廊下やトイレには足元照明を設置する
・よく使う物は腰〜胸の高さにまとめ、屈まず・背伸びせずに取れる位置に置く
こうした対策を行う際、「捨てる」という言葉を使わないことがポイントです。捨てる話だと思うと、不安や抵抗感が強まってしまいます。
「通れる道だけ一緒につくろう」「火の周り1mだけ安全にしよう」「捨てることじゃないから安心して安心して」のように伝えると、不安や抵抗感を和らげながら協力してもらいやすくなります。
一時的に物を移動させるのは「保留」であり、捨てるかどうかは後から決めれば構いません。まずは安全な動線を確保すること。それだけで、転倒や火災のリスクを大きく減らすことができます。
ステップ2:NG行動を知る。「どうして?」と責めない・無理強いしない
片付けの場面で最も避けたいのは、親を責めたり、無理に押し通したりして関係がこじれてしまうことです。正論や命令口調は逆効果になり、片付けが前に進まなくなります。
大切なのは「責めない・押しつけない」こと。言葉を少し言い換えるだけで、関係も効率も守ることができます。
たとえば「どうしてできないの?」と問い詰めるよりも、「今日は通路だけ10分見直してみようか?」と範囲を区切って提案した方が、相手も受け入れやすくなります。
また、「捨てるよ」と断言するのは控えてください。「写真に残してこの箱に一旦保管しよう。必要なら戻せるから」と伝えるだけで、安心感が生まれます。
次のように、片付けのときによく出てしまう言葉を少し変えるだけで、相手の受け止め方が大きく変わります。
| NGな言葉 | OKな言い換え |
| 「どうしてできないの?」 | 「今日は通路だけ10分見直してみようか?」 |
| 「捨てるよ」 | 「写真に残してこの箱に一旦保管しよう。必要なら戻せるから」 |
| 「前はできたでしょ」 | 「最近変わってきたところを一緒に工夫したい」 |
| 黙って片付ける | 必ず同意を得て「これは保留?残す?」と二択で確認する |
さらにスムーズに進めるために、片付けを始める前に「疲れたら今日はここで終わりにしよう」という合図の言葉をあらかじめ決めておくのも効果的です。 無理に続けてしまうより、親子の関係を優先できる安心材料になります。
また、長時間の作業は避け、10〜15分ごとに休憩を挟みましょう。片付いた場所があれば、「ここが通れるようになって助かったよ」といった言葉で感謝を伝えることで、より前向きな雰囲気を保つことができます。
ステップ3:本人の気持ちを尊重する。「ナッジ」で優しく促すコミュニケーション術
片付けのときに「正しいこと」を押しつけると、相手は不安や怒りで反発してしまいます。そこで役立つのが「ナッジ」という、行動をそっと促す考え方です。強制ではなく、自然に選びやすくなる工夫を取り入れることがポイントです。
「これは捨てて!」と迫るのではなく、「この箱に保留と書いて、3か月だけ置いてみようか?」のように提案すれば、相手の安心感は大きく変わります。
たとえば、次のような工夫が片付けのハードルをぐっと下げてくれます。
| 工夫の例 | 効果 |
| 迷ったら保管箱へ移す | 判断に迷う物はあとで見直せるようにすることで安心感が得られる |
| 出し入れを簡単にする | フタのない箱や透明ケースを使い、「どこにしまうか・どこにあるか」が一目でわかる安心感がある |
| 二択にする | 「よく使うのはAとBどっち?」と具体的に聞いて選びやすくする |
| 写真に残す | 手放す痛みを和らげつつ、記録として思い出を残せる |
声をかけるときも、「捨てる」「片付ける」といった言葉を前面に出すのではなく、安心できる表現に変えることが大切です。
ステップ4:すべてを一人で抱えない。外部の相談窓口を知っておく
親の家の片付けや生活環境の改善を、家族だけで背負おうとすると心身ともに疲弊し、親子関係もすり減ってしまいます。困ったときは「つながる」ことが大切です。相談先は大きく分けて公的な窓口と民間サービスがあります。
公的な相談窓口
| 相談先 | 具体的な内容・役割 |
| 地域包括支援センター | 高齢者支援の総合窓口。状況を相談すれば、認知機能の評価や介護保険サービスにつなげてもらえる。 |
| かかりつけ医 | 物忘れ・転倒・服薬の変化をメモして相談。医療的な視点で必要な支援へ導いてくれる。 |
| 社会福祉協議会・自治体 | 見守り訪問、家事援助、ごみ出し支援、福祉用具の情報提供など、地域のサポートを紹介。 |
民間サービス
| サービス | 具体的な内容・役割 |
| 整理収納支援 | 動線設計やラベリングで片付けやすい環境を整え、再発を防ぐ仕組みづくり。 |
| 不用品回収・清掃 | 保留を除いた不用品をまとめて搬出・処分。家族の負担を軽減。 |
| 福祉住環境の調整 | 手すり・照明・滑り止めの設置など、安全性を高める住環境改善を提案。 |
初めて相談するときは、「何を心配しているのか」「どのような支援を求めたいのか」を簡潔に伝えるとスムーズです。具体的に「親の様子」「困っていること」「求めたい支援」を3点セットで伝えるのがポイントです。
介護が必要な場合は「要介護認定」の手続きをおこなう必要も
認知症が進んでしまい、介護を受けなければならない状況となった場合には、介護保険の利用も検討しなければなりません。こちらの記事では、認知症と診断された時に必要な手続きやサービスについて解説をしております。ぜひご参考ください。
認知症の要介護認定とは?手順や介護保険サービスをかんたん解説|静岡老人ホーム紹介タウンYAYA
https://yaya-roujinhome.com/nursing-info/nursing-info-7752/
専門業者に頼るのは「親不孝」ではなく「新しい親孝行」という選択
「家族だから自分が何とかしなければ」という想いは尊いものです。
しかし、認知症による片付けの問題を家族だけで背負うには、あまりに大きな負担がのしかかります。
業者を頼ることは「親不孝」ではなく、「家族としての役割を投げ出すこと」でもありません。
本当に大切なのは「誰が片付けたか」ではなく、あなたの親が安全で安心できる暮らしを取り戻すことです。
業者に頼ることはむしろ、親の尊厳を守り、あなた自身も「優しい子供」として寄り添うための「新しい形の親孝行」です。
家族だから難しい…第三者のプロが入る3つのメリット
家族で片付けを進めようとすると、どうしても感情のぶつかり合いが起こりがちです。
「捨てて」「捨てないで」の繰り返しで関係がぎくしゃくしてしまうことも少なくありません。
そこで役立つのが、第三者である片付けのプロ。専門的な視点と中立的な立場から、家族では難しい部分をスムーズに進める3つのメリットをご紹介します。
メリット1:安心を手にできる
「業者に頼むなんて、親不孝では?」と感じる方は少なくありません。しかし、認知症による片付けの問題は、家族の努力だけで解決できるものではないのが現実です。
むしろ、無理に背負い続けることで親子関係がこじれたり、あなた自身の心身がすり減ってしまうリスクの方が大きいのです。
プロに頼むことは家族としての役割を手放すことではなく、親を守るために最適な役割分担をすること。
罪悪感ではなく、安心を得るための選択肢になります。
メリット2:外からの目を気にせず進められる
「近所に知られたら恥ずかしい」「親のプライドを傷つけたくない」という思いも、子どもとして自然な気持ちです。専門業者はプライバシーへの配慮を徹底しており、周囲に知られないように作業を進められます。
また、家族が伝えると「責められている」と受け取られやすい言葉も、第三者のプロであれば提案として受け止めてもらいやすいのも大きな違いです。親の尊厳を守りながら片付けを進められるのも大きなメリットです。
メリット3:一気に解決できる行動力
ゴミ屋敷化した家を家族だけで片付けるのは、体力的にも精神的にも大きな負担で、つい先延ばしになりがちです。そして、その間に状況は悪化していきます。
プロに依頼すれば、数か月かかるような作業をわずか数時間から数日で一気に進め、安全な環境を取り戻せます。
さらに、ただ片付けるだけでなく、再び散らかりにくくする工夫(ラベル付け・保留箱・動線設計)まで整えてくれるのがプロの強みです。安心できる暮らしを今日から取り戻すことができます。
「優しい子供」でいる時間を増やすために、私たちができること
親の家を片付ける時間が増えるほど、あなたは「注意する人」「叱る人」として振る舞わざるを得なくなり、心の距離まで広がってしまいます。
本当は心配しているだけなのに、「どうして片付けないの?」「どうしてできないの?」…そのようなやり取りを繰り返すうちに、本来の「優しい子ども」として寄り添う時間も減っていきます。
私たちの役割は、ただ物を処分することではありません。衝突のきっかけになりやすい片付けを第三者の私たちが引き受けることで、あなたは親と穏やかに向き合える時間を取り戻せます。
「優しい子供」でいる時間を増やすために、私たちができること
・親の安全を守る
・あなたの心を守る
・家族の絆を守る
「業者を頼むのは親不孝ではないか」と迷う気持ちは自然なことです。しかし実際には、親の尊厳を守りつつ、あなた自身も無理せず支え続けるための新しい形の親孝行。それが、私たちができることです。
後悔しない専門業者の見つけ方と、私たちにできること
専門業者に依頼することは、親の安全と安心を守る大切な選択です。
しかし、「どの業者を選ぶか」で、その後の状況は大きく変わります。経験や対応姿勢が不十分な業者に当たってしまうと、後悔や不安を抱える原因になりかねません。
ここでは、後悔しないために確認すべき3つのポイントと、私たち「お助けうさぎ」がご家族にどのように寄り添うことができるのかをご紹介します。
確認すべき3つのポイント(実績・料金の透明性・人柄)
専門業者を選ぶときに大切なのは、「誰に頼んでも同じ」ではない、という視点です。実績や料金、人柄の3つをしっかり見極めることで、後悔のない依頼につながります。
1. 実績:高齢世帯や認知症の方のお宅での経験があるか
不用品回収の経験が豊富でも、高齢者や認知症世帯の経験がなければ安心して任せられません。ビフォーアフターの事例や口コミを確認し、どの程度似たようなケースでの実績があるかを確認しましょう。
2. 料金の透明性:見積りの内訳が具体的か
片付けサービスは料金体系が分かりにくいこともあります。必ず事前に現地またはオンラインでの見積りを受け、作業範囲・人数・時間・搬出量・追加条件まで具体的に書面で確認しましょう。
家電リサイクル費や自治体処分費などの実費と、人件費やサービス費を分けて提示してくれるかも重要です。さらに、キャンセル規定や支払い方法(現金・振込・カードなど)も事前に明示してくれる業者を選ぶと安心です。
3. 人柄:尊厳を守る姿勢か
業者にとってスピードや効率も重要ですが、それ以上に大切なのは「親の気持ちや尊厳をきちんと守ってくれるかどうか」です。
勝手に処分せず、必ずご本人やご家族の合意を確認しながら進める。写真や保留箱を活用し、「残す/保留」の選択肢を常に提示する。そうした丁寧さが業者の姿勢に表れます。
作業中の声かけ、個人情報や写真の取り扱いルールなども信頼のバロメーターになります。
私たちは単なる作業員ではありません。ご家族に寄り添う「片付けのパートナー」です
私たち「お助けうさぎ」は、不用品をただ回収するだけの業者ではありません。
ご家族の思いを尊重し、事前の見積りや相談を通じて合意を取りながら作業を進めることを大切にしています。
また、女性スタッフの同行や秘密厳守の体制、損害賠償保険への加入や資格を持ったスタッフによる作業で、安全性と信頼性を確保しています。
「家族だから自分が頑張らなきゃ」と思う気持ちは尊いものです。しかし、それを一人で抱え続ける必要はありません。むしろ無理を重ねてしまうと、親子関係がすり減ってしまうこともあります。
私たちは、ご家族が「優しい子ども」として寄り添える時間を増やすためのパートナーでありたいと考えています。
まずはご相談だけでも大丈夫です。お話しいただければ、最適な解決の方法を一緒に考えられます。
迷ったまま立ち止まるよりも、まずは気持ちを少し軽くしてみませんか?
まとめ:一人で抱え込まず、まずは専門家へ相談することから始めましょう
親が片付けられなくなる背景には、認知機能の低下・心理的な不安・身体的な衰えといった複数の要因があります。これは「だらしないから」ではなく、誰にでも起こりうる自然な変化です。
家族にできることは、安全を最優先にした環境づくりや、責めない声かけ、小さな工夫の積み重ねです。ただし、家族だけで抱え続けると関係がこじれたり、あなた自身が疲れ果ててしまうリスクも大きくなります。
そのようなとき頼れるのが、公的な支援窓口や片付けの専門業者です。第三者の力を借りることは決して「親不孝」ではなく、親の尊厳と安全を守るための新しい形の親孝行です。
大切なのは「誰が片付けたか」ではなく、「安心して暮らせる環境をどう取り戻せるか」。
一人で背負い込む必要はありません。まずは身近な相談先や専門家に相談することから、無理のない一歩を踏み出してみてください。