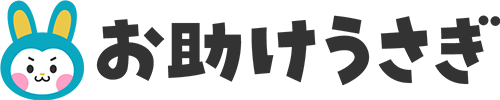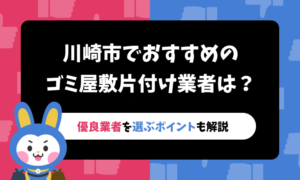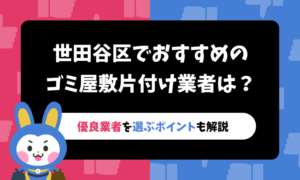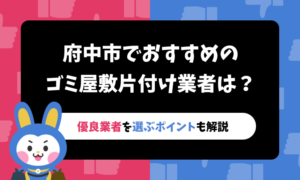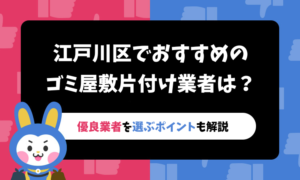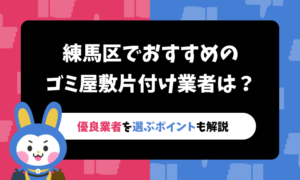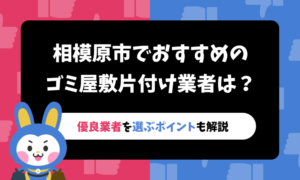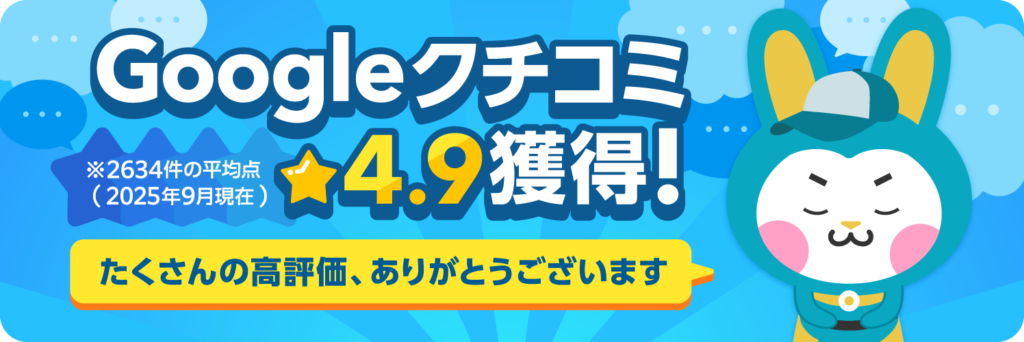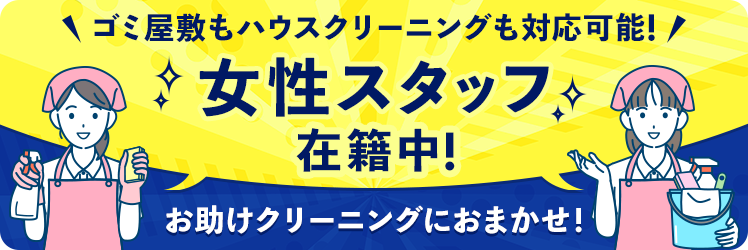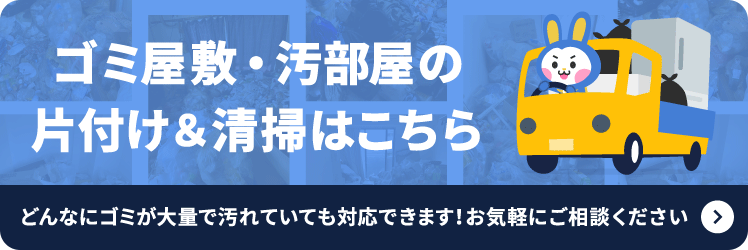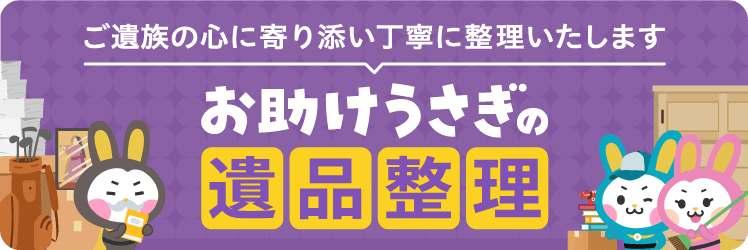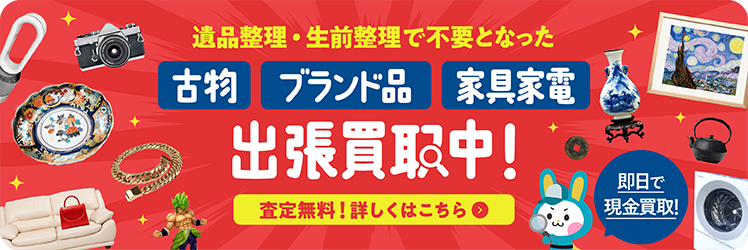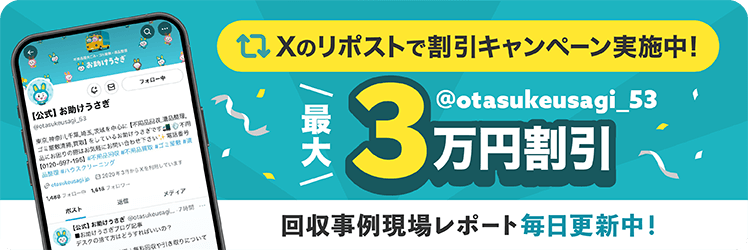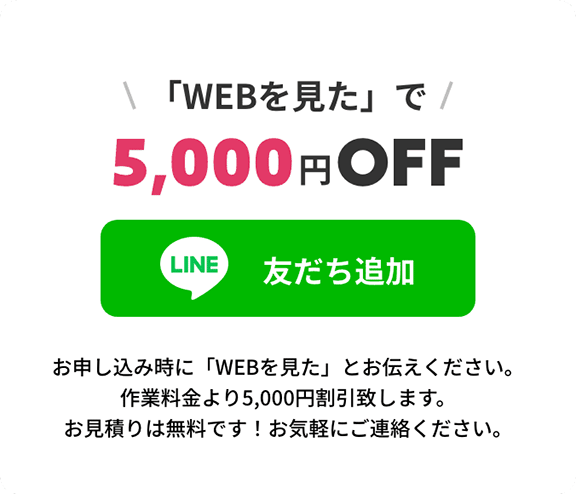お守りの返納方法は?|捨て方や処分方法を解説
不用品別の処分方法ゴミ屋敷の問題は、誰にも言えず、ひとりで抱え込んでしまいがちです。
「自分の家が…」「親の家が…」「近所の家が…」状況はさまざまでも、共通しているのは「何から始めればいいかわからない」という戸惑いや不安ではないでしょうか。
この記事では、自宅の問題・家族の問題・近所の問題というそれぞれのケース別に、最適な相談先と解決までの具体的な流れをまとめました。
まずは、あなたの状況に近いところから確認してみてください。ひとりで抱え込んでいた悩みを解決するきっかけになると思います。
この記事を読むと以下のことが分かります。
・ゴミ屋敷の状況別相談先
・相談前に準備しておくべきこと
・相談先へ伝えるコツ
・専門業者への相談が解決への近道である理由
ゴミ屋敷の悩み、一人で抱えずに相談しませんか?
「もう自分ではどうにもできない」
「このままではいけないのに、何をどうすればいいのかわからない」
そのような不安や焦りを抱えている方も少なくありません。
ゴミ屋敷の問題は、誰かに打ち明けることさえ難しく、ひとりで抱え込んでしまいがちです。しかし、状況に合った正しい情報さえわかれば、必ずできることがあります。
この記事では
・ご自身の家がゴミ屋敷になってしまった場合
・ご家族の家がゴミ屋敷になってしまった場合
・ご近所の家がゴミ屋敷化している場合
という3つの状況に分けて、それぞれに合った相談先と解決までの流れを整理しています。
誰にも言えず、ひとりで抱え込んでしまうことが多いゴミ屋敷の問題も、正しい知識と適切な相談先を知ることで、「何から始めればいいのか」が見えてきます。
この記事が、問題解決のきっかけになれば幸いです。
「どこに相談すれば…」という悩みに応える完全ガイドです
ゴミ屋敷の問題は、家の中というプライベートな領域に関わるため、当事者だけでなく家族や周囲の人にとっても、扱いが難しい問題です。
- 誰にも知られたくない
- 自分で片付けられない
- 家族や他人の家にどこまで関わっていいかわからない
といった法的・心理的な制約も多く、ただの掃除の問題では済まされない現実があります。
さらに、相談できる窓口は行政・保健所・警察・専門業者など複数あるものの、それぞれがどこまで対応してくれるのか役割が見えづらいことも、行動をためらう原因の一つです。
だからこそ大事なのは、自分の状況に合った「正しい相談先」を知ることです。この記事では、当事者・家族・近隣などそれぞれの立場に応じた最適な相談先と、相談後の流れを具体的に解説しています。
まずあなたの状況は?3つのケースから最適な相談先を見つけよう
ゴミ屋敷の問題は、「誰の家なのか」「どんな関係なのか」によって、相談すべき先も対処方法も大きく変わってきます。
この記事では、次の3つのケースに分けて、それぞれに最適な相談先と対処法を詳しく解説しています。
状況別:3つのケース
・Case 1:ご自身の家がゴミ屋敷になってしまった方
・Case 2:親や親族の家がゴミ屋敷でお困りの方
・Case 3:近隣の家がゴミ屋敷で迷惑している方
まずは、ご自身の状況にもっとも近いケースから確認してみてください。
Case 1:ご自身の家がゴミ屋敷になってしまった方
「恥ずかしくて誰にも言えない」
「片付けたい気持ちはあるけど、どう手をつければいいのかわからない」
そのように悩んでいる方は、決して少なくありません。
ゴミ屋敷の悩みは、とても個人的で、人に知られたくない思いも強くなりがちです。そのような方に向けて人に知られずに相談できる方法をご紹介しています。
無理なく自分のペースで動き出すために、まずは相談先を確認してみてください。
Case 2:親や親族の家がゴミ屋敷でお困りの方
親や兄弟姉妹、親戚の家がゴミ屋敷になってしまい、心配は募るものの、どう踏み込めばいいのかわからない。そのようなもどかしさを抱えている方が多いのではないでしょうか。
たとえ家族でも、本人が問題を認めていなかったり、片付けを拒んでいたりすると、無理に動くことは逆効果になることもあります。
そのような状況で悩んでいる方に向けて、家族の立場から相談できる具体的な窓口を紹介します。
⇒親や親族の家がゴミ屋敷でお困りの方について、相談窓口一覧はこちら
Case 3:近隣の家がゴミ屋敷で迷惑している方
悪臭や害虫の発生、ゴミの越境など、近隣のゴミ屋敷が日常生活に支障をきたしているケースは少なくありません。
とはいえ、本人に直接伝えるのは難しく、余計なトラブルを避けたいというのが本音ではないでしょうか。
そこで、公的機関や管理者など、第三者として相談できる窓口を整理しました。相手とのトラブルを避けながら、自分の生活を守る手段を見つけてください。
⇒近隣の家がゴミ屋敷で迷惑している方について、相談窓口一覧はこちら
【ケース別】ゴミ屋敷の具体的な相談窓口一覧
ゴミ屋敷の問題は「誰の家なのか」「どのような関係性なのか」によって、相談すべき相手や支援の受け方がまったく異なります。
ここでは、ご自身・ご家族・近隣住民という3つのケースに分けて、それぞれの相談先と、その役割や特徴について解説します。
Case 1:自分の家を相談したい場合
「片付けたい気持ちはある。でも、どこから手をつければいいかわからない」「見られるのが恥ずかしくて、誰にも言えない」そうした気持ちの中で、ずっとひとりで悩みを抱えていませんか。
ゴミ屋敷の問題は、精神的な負担や生活環境の悪化が複雑に絡み合い、ひとりではどうにもできない状態に陥ってしまうこともあります。
しかし、相談することで状況が動き出す可能性は十分にあるでしょう。以下では、「誰にも知られたくない」という気持ちに配慮しながらも、実際に頼れる窓口を3つご紹介します。
① 専門の片付け業者
ご自宅がゴミ屋敷化してしまった場合、まず相談しやすいのが片付け専門業者です。
最近は「無料相談」や「匿名での問い合わせ」に対応している業者も増えており、LINEやメールだけでやり取りできるところもあります。誰にも会わずに、安心して相談を始められる環境が整っています。
また、秘密厳守は業者側も徹底しており、依頼者のプライバシーを守ることは最優先事項です。作業当日も、目立たない車両や服装で対応するなど、近所に知られないよう最大限の配慮がされています。
「見積もりだけ取ってみる」「まずは話だけ聞いてみる」だけでもかまいません。現状を話すだけでも、気持ちが少し軽くなるはずです。
② 自治体の福祉課・生活相談窓口
ゴミ屋敷になってしまう背景には、単なる「片付けの苦手さ」だけではなく、経済的な困窮や、精神的な不調が関係していることも少なくありません。
もし生活に不安があったり、日常的なことが手につかないような状態が続いているなら、自治体の福祉課や生活支援窓口に相談してみることも検討しましょう。
こうした公的な窓口では、生活保護や一時的な住居支援、福祉サービスの利用といった支援につながる可能性があります。
また、「ゴミ屋敷をなんとかしたい」と伝えるだけでも、状況に応じて他の支援機関を紹介してくれることがあります。
身の回りの片付けだけでなく、生活そのものの立て直しを見据えた支援が必要な場合には、まずは一度、地域の相談窓口に相談してみてください。
③ 心療内科・精神科
「片付けなければと思っているのに、どうしても体が動かない」
「自分の意思ではどうにもできない」
そうした状態が長く続いているなら、単なる怠けや意思の問題ではなく、うつ病や発達障害、認知機能の低下など、精神的な不調が関係している可能性もあります。
実際、ゴミ屋敷の背景にあるケースとして心の健康の問題が見過ごされていることは少なくありません。
そのため、片付けの前に、まずは心療内科や精神科を受診することが、根本的な改善につながる場合もあります。
片付けられない自分を責めるのではなく、まずは心と体の状態を見直すことも、状況を変えるきっかけになります。
Case 2:親・家族の家を相談したい場合
親や親族の家がゴミ屋敷化してしまった場合、「どう介入すべきか」「誰に相談すれば動いてくれるのか」と迷う方は少なくありません。家族だからこそ距離感が難しく、ご本人の拒否感が強い場合はなおさらです。
そうしたときに頼れるのが、以下のような専門的な相談先です。
① 地域包括支援センター
親や親族が高齢で、住まいがゴミ屋敷のような状態になっている場合、まず相談すべき窓口が地域包括支援センターです。
地域包括支援センターは全国の市区町村に設置されている高齢者支援の総合窓口で、介護・福祉・医療・生活支援といった多方面の課題に対応できる体制が整っています。
たとえば以下のようなケースに、地域包括支援センターが関与できます。
・認知症の疑いがあり、日常生活に支障が出ている
・ゴミや不用品が溜まりすぎており、転倒や火災のリスクがある
・食事・服薬・清潔保持など、生活全体が立ち行かなくなっている
・家族が本人と直接話し合えない、または拒絶されている
地域包括支援センターには保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーなどの専門職が常駐しており、状況を聞き取ったうえで、制度の活用や民間・行政の支援サービスとの連携を多角的に提案してもらえます。
高齢者本人が問題を自覚していなかったり、片付けを拒否しているような場合でも、家族からの相談をきっかけに、第三者としての専門職が介入する形で支援の糸口が見つかることもあります。
② 自治体の高齢福祉課・保健所
高齢の親や家族の住まいがゴミ屋敷状態になっている場合、地域包括支援センターだけでなく、自治体の高齢福祉課や保健所も重要な相談先です。
福祉課や保健所は、地域包括支援センターと連携しながら、より具体的な制度的支援の申請や行政的な対応を担っています。
たとえば以下のようなケースで関与することがあります。
・ゴミや不衛生な環境が近隣にも影響を及ぼしている
・本人が介護認定を受けておらず、生活支援が一切入っていない
・認知症や精神疾患が疑われるが、医療につながっていない
・虐待やネグレクトが疑われる(セルフネグレクトを含む)
地域包括支援センターが相談の窓口であるのに対し、高齢福祉課や保健所は実際の行政判断や制度適用の中核となる立場です。
センターからの紹介でつながるケースが多いですが、緊急性が高い場合は直接相談することも可能です。
家族の立場でできることには限りがあります。状況が深刻化する前に、こうした公的な窓口も相談先の一つとして視野に入れておくと、対応の幅が広がります。
③ ケアマネージャー(すでに担当がいる場合)
すでに介護サービスを受けており、ケアマネージャーがついている場合は、もっとも身近で信頼できる相談相手です。
本人が介護サービスを受け入れている状態であれば、外部の人間としてではなく、信頼関係がすでにある支援者として、よりスムーズに話を進められます。
具体的には以下のような対応が期待できます。
・本人に無理のない形で現状を伝える
・ゴミや不用品の片付けを含めたケアプランの見直し
・必要に応じて地域包括支援センターや医療機関との連携
・福祉用具・生活支援サービスの追加手配
また、本人が片付けに抵抗感を持っている場合でも、ケアマネージャーのような第三者が必要性を伝えるアプローチであれば、説得しやすくなる場合もあります。
ただし、「片付け」は直接の業務外になるため、他の機関や業者との連携を進める窓口役として活用すると効果的です。
④ 専門の片付け業者
本人が片付けに同意したのち、実際に手を動かして現場を改善してくれるのが、ゴミ屋敷片付け業者です。
多くの業者は無料見積もりや作業内容の説明を丁寧に行い、写真付きの資料や実績をもとに提案してもらえます。
「何をどのように片付けるのか」「費用はどのくらいかかるのか」「どの程度の時間で終わるのか」などが具体的に見えると、ご本人も安心しやすく、片付けに前向きになるケースが多いです。
また、ゴミの分別から搬出・清掃・消臭・不用品の買取や廃棄の手配まですべてを一括で対応してくれる業者も多く、ご家族の身体的・精神的な負担を大きく軽減してくれます。
Case 3:近所の家について相談したい場合
近隣の家がゴミ屋敷化し、悪臭や害虫、ゴミの越境といった実害に悩まされていても、直接本人に苦情を伝えるのはトラブルの原因になりかねません。
「どこに相談すればいいのか分からない」「誰に伝えるのが適切なのか迷っている」そのような状況にいる方に向けて、物件の形態や被害の内容に応じた相談先を紹介します。
トラブルを避けつつ、自分や家族の生活を守るため、適切な窓口の利用をおすすめします。
① 賃貸なら管理会社・大家
対象の物件が賃貸住宅である場合、まず相談すべきは物件の管理会社または大家(貸主)です。
管理者には、建物全体の衛生・安全・住環境を保つ責任があり、賃貸借契約や管理規約に基づき、入居者の迷惑行為に対応する義務があります。
たとえば、室内のゴミによる悪臭や害虫が発生している、共用部へゴミが出ているといった状況は、明確な「契約違反」や「善管注意義務違反(善良な管理者の注意義務違反)」にあたる可能性があります。
そのため、管理者が是正指導や契約上の措置(注意喚起、警告、契約解除など)を講じることが可能です。
相談の際には、「どの部屋か」「どのような被害が出ているか」を明確に伝えることで、対応もスムーズになります。匿名での通報に対応してくれる管理会社も多く、本人との直接対立を避けながら問題を解決できます。
迅速な対応が期待でき、トラブルを最小限に抑えられる相談先として、まずは管理者や大家(貸主)への相談を検討してみましょう。
② 戸建てなら自治体の環境課・生活衛生課など
近隣の住宅が戸建てである場合、公的な相談先として有効なのが、自治体の環境課や生活環境関連の窓口です。
多くの自治体では、悪臭や害虫の発生、ゴミの越境といった生活環境への被害について、住民からの相談を受け付けています。
地域によっては、「ゴミ屋敷条例」(正式には「生活環境保全条例」など)が整備されており、相談を受けた自治体が以下のような対応をしてくれる場合があります。
・現地調査(実際に職員が現場を確認)
・本人への注意や指導(手紙や訪問による)
・状況が改善されない場合の勧告や命令
ただし、これらの対応には時間がかかることも多く、強制的な片付けや立ち入りにより即時解決とはいきません。
とはいえ、公的な対応が入ることで、本人が事態を重く受け止めるきっかけになることもあります。
まずは自治体の公式サイトや窓口に問い合わせて、どの部署が担当かを確認し、相談をしてみましょう。
③ 警察
近隣のゴミ屋敷が原因で「道路にはみ出したゴミが通行の妨げになっている」「不審な人物が頻繁に出入りしている」など、安全や治安に関わる懸念がある場合は、警察への相談が有効です。
警察は「道路交通法違反」「軽犯罪法違反」など、法令に抵触する可能性のあるケースに対応する権限を持っています。
公共の通行を妨げるケースや、治安上の不安がある場合は、警察に現状を伝えて判断を仰ぐことで、現地確認や注意喚起などの対応につながることがあります。
ただし、民事不介入の原則により、ゴミの量が多い・不衛生といった私有地内での問題そのものには介入できません。
それでも、「通行妨害がある」「異常な出入りが続いている」など違法性が疑われる状況であれば、十分に相談対象となります。
相談の際には、日時・状況・写真などの記録を用意しておくと、よりスムーズに相談が可能です。
④ 消防署
ゴミ屋敷が原因で「火の気はないのに焦げくさい」「室内に可燃物が山積みで火災が心配」など、火災のリスクが現実的に考えられる場合は、消防署への相談が有効です。
消防署は、住宅の火災予防に関して指導・助言の権限を持つ機関です。現場の状況によっては、住人に対して「消防法に基づいた予防的な指導」を行い、改善を促すことがあります。
特に「延焼のおそれがある」「電気火災につながりかねない状態」など、近隣にも危険が及ぶと判断される場合、対応が迅速になる傾向があります。
ただし、消防署の対応はあくまで「指導」にとどまり、片付けの代行や強制的な撤去措置は行っていません。
そのため、消防署への相談は、火災の未然防止や住人への注意喚起を目的としたきっかけ作りとして活用しましょう。
相談する前に!準備しておくべきことと伝え方のコツ
ゴミ屋敷について相談する際、「なんとなく困っている」だけでは、公的機関や専門業者に正確に状況を伝えられず、十分な対応が受けられないこともあります。
スムーズに話を進めるためには、事前の準備が欠かせません。状況を整理し、必要な情報や証拠をそろえておくだけでも、相談先から適切な支援を受けやすくなります。
ここでは、相談前に確認しておきたい3つの準備項目を、チェックリスト形式で具体的に解説します。
状況を整理する:5W1Hで情報をまとめる
相談時に「何がどれだけ深刻なのか」が伝わらなければ、的確な対応を受けにくくなります。
そのため、あらかじめ状況を 5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうしたいか) の視点で整理しておくことが重要です。
以下のような情報をメモしておくと、相談窓口でも話がスムーズに進みます。
相談する前に準備しておくべき5W1H
・いつからその状態か(例:ここ数年で急にゴミが増えた)
・どこの場所か(例:〇〇市〇〇町の戸建て、集合住宅の一室など)
・誰の住まいか(例:自分/親/親戚/隣人 など)
・どんな状況か(例:玄関までゴミが積まれている、異臭が強い)
・何に困っているか(例:本人の健康状態、近隣からの苦情)
・どうしたいのか(例:本人に片付けを促したい、専門家に入ってほしい)
相談先が状況を正確に把握できれば、対応方法やアドバイスの質も高くなります。まずはご自身の言葉で、状況を整理してみてください。
証拠を用意する
特に第三者(家族・近隣住民など)が相談する場合、客観的な証拠の有無で対応の質・スピードが変わることもあります。
実情を正確に把握しない限り動きにくく、ただ「困っている」と伝えるだけでは対応が後回しになることもあるからです。
以下のような情報や記録を用意しておくと、公的機関や管理者に状況の深刻さを伝えやすくなります。
相談する前に準備しておくべき証拠
・ゴミが建物外にはみ出している写真や動画
・害虫や異臭が発生している状況の写真や動画
・悪臭の発生状況や害虫の出現頻度を記録したメモ(日付・時間・具体的な被害内容など)
・苦情や被害を受けた履歴(近隣住民とのやりとり、トラブル発生の経緯など)
こうした証拠があれば、相談先も事態の深刻さを把握しやすく、より迅速かつ具体的な対応につながります。
感情的にならず、客観的な事実を伝える
ゴミ屋敷の問題に直面すると、つい「とにかく不潔で我慢できない」「常識では考えられない」など、感情的に訴えたくなる場面もあるでしょう。
しかし、行政や専門機関に相談する際は、できるだけ冷静に、客観的な事実として伝えることが大切です。
たとえば、次のように状況を説明することで、対応窓口側も現状の深刻さを理解しやすくなります。
| 良くない例 | いい例 |
| 「とにかく臭くて不潔」 | 「生ゴミの腐敗臭が強く、窓を開けられない状態が1週間以上続いています」 |
| 「虫がわいて気持ち悪い」 | 「台所周辺からハエやゴキブリが発生しており、建物共用部(周辺の家)にも影響が出ています」 |
| 「もう限界!毎日迷惑してる」 | 「玄関前にゴミが積まれ、悪臭や虫の発生により、住民の通行に支障が出ています」 |
| 「火事になったら怖い」 | 「室内外に可燃物が多く、火災発生時に延焼リスクが非常に高い構造になっています」 |
このように、感情的な訴えよりも、客観的な事実として伝える工夫をすることで、相談先に「対応の必要性」が伝わりやすくなり、動いてもらえる可能性が高まります。
専門業者への相談が最終的な解決への近道である理由
ゴミ屋敷の問題は、放置するほど深刻化します。悪臭や害虫の発生、近隣トラブルが増え、精神的に追い詰められる方も少なくありません。
行政や自治体などの相談窓口は複数ありますが、実際に現場を「片付ける」作業までしてくれるわけではありません。
問題を根本的に解決できるのは、現場に入り、具体的な作業まで一貫して対応できる専門業者だけです。
「どこに相談しても状況が変わらない」と感じている方も、専門業者に依頼することで、初めて目に見える改善を実感できます。
ここでは、公的機関と専門業者の違いを整理しながら、なぜ専門業者に相談することがゴミ屋敷問題の最終的な解決につながるのか、詳しくご説明します。
公的機関の限界:相談はできても「片付け」はしてくれない
ゴミ屋敷の解決方法を探す際、まず思い浮かぶのが自治体や保健所などの公的機関かもしれません。
しかし、公的機関が対応できるのは、あくまでも「助言」や「指導」、あるいは状況に応じた支援制度の紹介まで。実際に家の中に入り、大量に積まれたゴミを分別し、処分するような作業は行ってくれません。
役所に相談しても、あくまで間接的な対応が中心になります。実際に手を動かし、物理的に状況を改善するのは、制度や役割の面で難しいのが現実です。
そのため、本当にゴミ屋敷を改善したいと考えたとき、現場での実務を任せられる専門業者に相談することが必要になります。専門業者であれば、ゴミの分別から搬出・処分・清掃までを一貫して行い、直接的に問題を解決できます。
「相談しても何も変わらない」「結局、どうにもならない」と諦めてしまう前に、具体的な解決手段を持つ専門業者への依頼を検討してみてください。
専門業者ならできること
公的機関に相談しても、実際の「片付け作業」まではやってくれません。
しかし、専門業者であれば、ゴミの処理から衛生対策まで一括して対応します。たとえば、以下のような作業をまとめて任せることが可能です。
専門業者に任せられる作業例
・即日対応・土日対応など、迅速なスケジュール調整
・ゴミの仕分け・分別・搬出・処分まで、すべて代行
・消臭・除菌・害虫駆除など衛生面の徹底処理
・リユース可能な不用品の買取対応でコスト負担を軽減
・本人や家族の精神的・肉体的負担を最小限に抑える対応
人目が気になる場合でも、目立たない車両や服装での作業、時間帯の配慮など、プライバシーに配慮した対応も行っています。
「どこに相談しても動かない」「どうしていいかわからない」そのような状況こそ、専門業者の力を借りるタイミングかもしれません。
まずは、相談だけでも構いません。お話しいただくだけでも、状況が整理されることがあります。お気軽にご連絡ください。
お助けうさぎの無料相談でできること・安心のポイント
お助けうさぎでは、初めてご相談いただく方にも安心してご利用いただけるよう、以下のようなサポート体制を整えています。
専門業者に任せられる作業例
・無料相談・無料見積もり対応(お電話・メール・LINEなどでOK)
・秘密厳守・ご近所に知られない配慮ある作業体制
・事前見積もり以上の追加料金は一切なし
・分割払いや各種お支払方法にも柔軟に対応
・女性スタッフによる対応も可能(※要事前相談)
「片付けるかどうかはまだ決めていない」「まずは状況を相談したい」そのようなご連絡でもかまいません。
無理な営業は一切いたしませんので、安心してご相談ください。
まとめ:正しい相談先を見つけて、ゴミ屋敷問題解決への第一歩を
ゴミ屋敷の問題は、放置すればするほど状況が悪化し、周囲との関係性や健康・安全にも深刻な影響を及ぼします。
しかし、状況に合った適切な相談先を知り、正しい手順で行動すれば、必ず解決に向かうことができるはずです。ここで改めて、相談先を整理しておきましょう。
状況別に見る最適な相談先のおさらい
Case 1:ご自身の家がゴミ屋敷になってしまった場合
・専門の片付け業者(匿名相談・秘密厳守で相談しやすい)
・自治体の福祉課・相談窓口(生活支援や制度の活用)
・心療内科・精神科の医師(精神的な不調が背景にある場合)
Case 2:親や家族の家がゴミ屋敷になっている場合
・地域包括支援センター(高齢者支援の総合窓口)
・自治体の高齢福祉課・保健所(連携支援)
・ケアマネージャー(既存の介護体制との連携)
・専門の片付け業者(同意後の具体的な作業実行)
Case 3:近隣の家がゴミ屋敷化していて困っている場合
・管理会社・大家(賃貸の場合の最優先相談先)
・自治体の環境課・専門窓口(戸建て・地域全体の問題)
・警察・消防署(安全上の問題がある場合のみ)
一人で悩まず、まずは相談することから始めましょう
片付けなければと思いながら、何もできないまま時間だけが過ぎていく。
見られるのが怖い。誰かに知られるのが恥ずかしい。
気づけば、自分でもどうしていいのかわからなくなっていた。
それでも、心のどこかでは「このままではいけない」と感じているかたがほとんどです。
ただ、実際に動こうとすると、何から始めればいいのかもわからず、考える余裕すらなかったのではないでしょうか。
片付けは、ひとりで抱え込むものではありません。むしろ、すべて自分で何とかしようとするほど、心も体もすり減っていきます。
私たちは、これまで多くのゴミ屋敷の片付けを行ってきました。
「誰にも知られたくなかった」「どうしていいのか分からなかった」そのような声を受け止めながら、現場に向き合ってきました。
どんな部屋でも、状況に合わせて、片付け・不用品の回収・清掃・消臭など、必要な対応を行っています。
弊社では、無料・匿名でのご相談も受け付けております。
状況を話していただくだけでも結構です。
無理に決断しなくてもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください。
⇒ご相談・お問い合わせはこちら