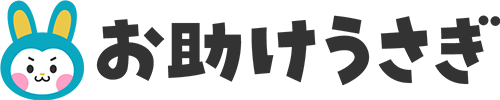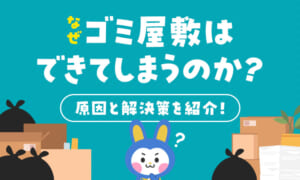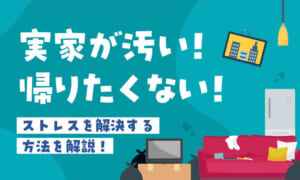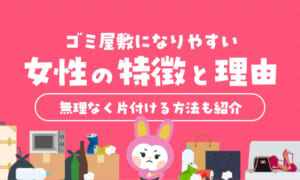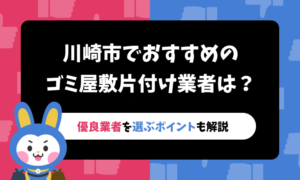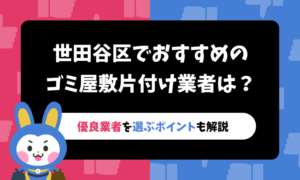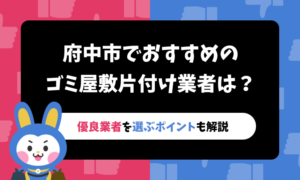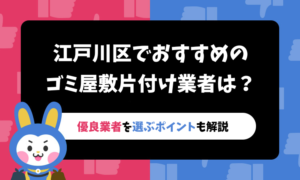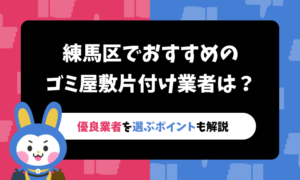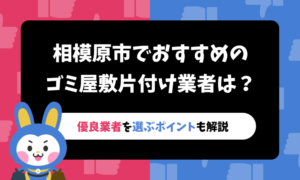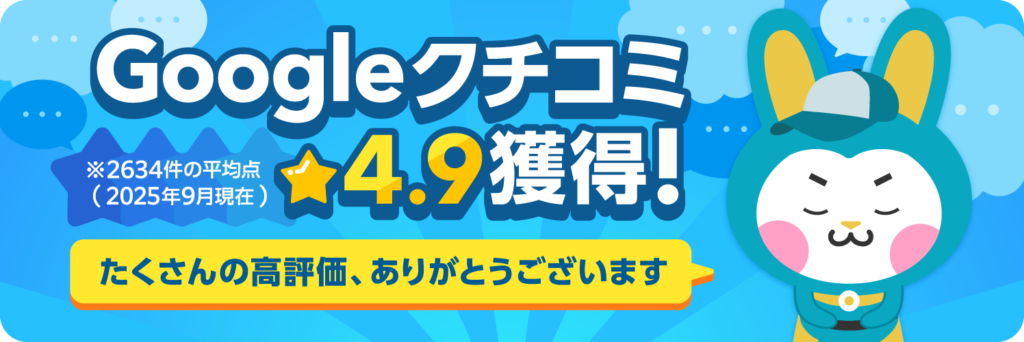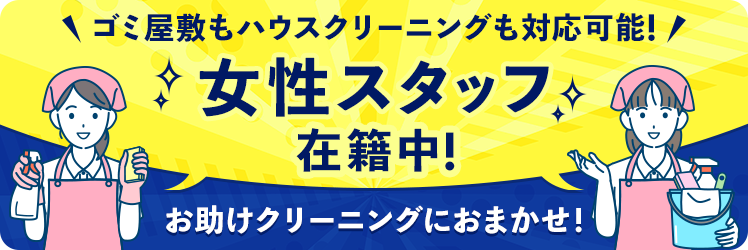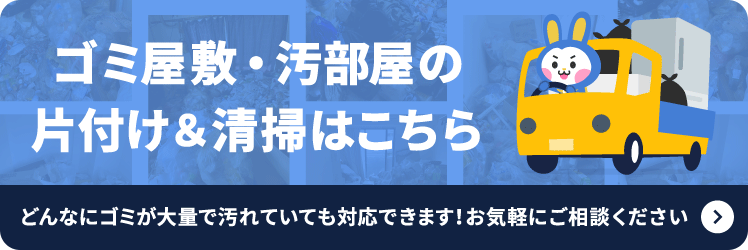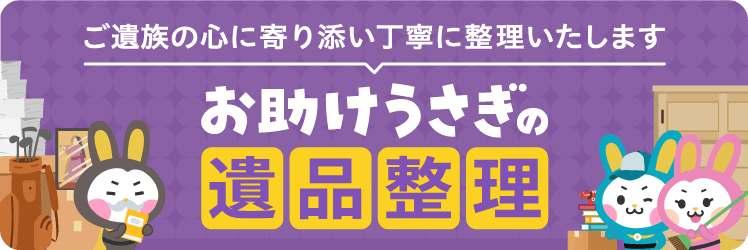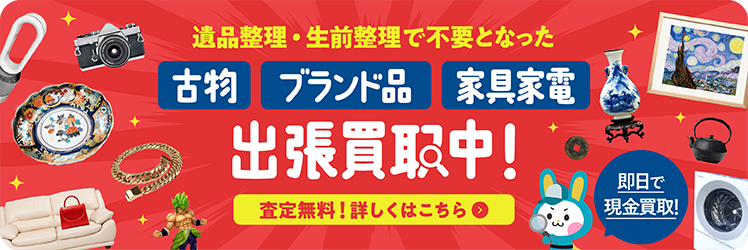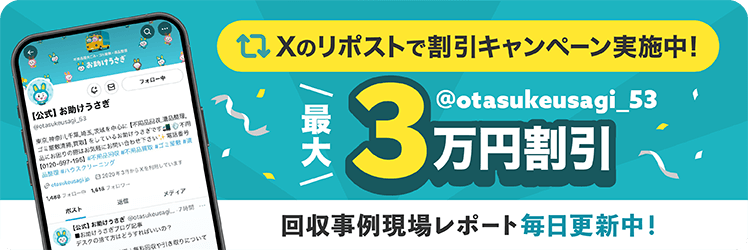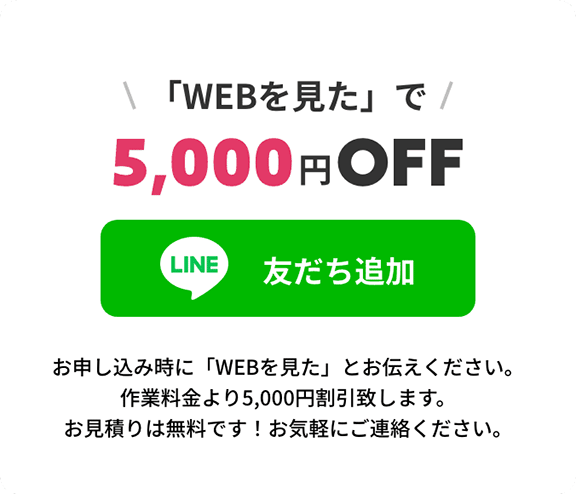お守りの返納方法は?|捨て方や処分方法を解説
不用品別の処分方法親の家がゴミ屋敷に…その悩み、一人で抱え込んでいませんか?
親の生活をなんとか取り戻してあげたい。
心配でたまらないけれど、何を言っても変わらず苛立ちばかりがつのる。
自分の親なのだから自分がしっかり解決しなければいけないのに、もう限界だ。
そのお気持ち、痛いほどわかります。親を思うからこそ、こうした気持ちを抱え一人で悩んでしまいますが、まずはその心の負担を軽減させることに目を向けてみましょう。この記事は、親の家のゴミ屋敷の解決に向けて具体的な一歩を踏み出すためのガイドブックです。
これは「家族の問題」であり、一人で解決できるものではありません
気付いたときには実家がゴミ屋敷になっていた、という状況は決して珍しくありません。自身の仕事や家事が忙しくて実家に帰る機会が減っていたことなどがあると「もっと早く気付いていれば……」と感じてしまいがちですが、近年では高齢者のゴミ屋敷の増加が社会問題になっており、このような状況は誰にでも起こり得ることです。
たとえ自分の親だとしても、ゴミ屋敷問題は「家族の問題」であり、あなただけのせいではありません。まずは一人で抱え込まないことが大切です。ゴミ屋敷の解決には、正しい知識と外部のサポートが必要であることを忘れず、ご自身を責めないようにしましょう。
なぜ親はゴミ屋敷にしてしまうのか?「片付けて」が通用しない理由
何度も片付けてと伝えているのに状況が変わらないと、伝える側もイライラしてしまいますよね。捨てようにも「ゴミじゃない」と抵抗されてしまうこともあるでしょう。このように言うことを聞いてくれないことはよくありますが、こうした言動の背景には理由が隠されています。そのため、むやみに叱責するのではなく、まずは原因を理解することが重要です。ここでは「片付けて」が通用しない親の心理を解説します。
親の「これはゴミじゃない」に隠された心理とは
ゴミ屋敷のゴミを指摘した際の「これはゴミじゃない」という発言はよく耳にする言葉です。これにはさまざまな心理が関係しています。
その一つが「もったいない」という価値観です。いつか使えるかもしれないと思うと捨てることに迷いが生まれます。もったいないという考え方は日本人の美徳とも捉えられる一面があるため、まだ使えるかもしれないのに捨てること自体に罪悪感を抱くこともあるでしょう。
また、物を溜め込み手放すことができない「ためこみ症(ホーディング障害)」という症状もあります。背景にある心理はさまざまですが、物に囲まれて安心感を得ていたり、孤独や不安などの感情を埋めていたりするケースがあります。過去の思い出に強い執着があり、捨てられなくなることもあるでしょう。
このような心理でゴミ屋敷になっている場合、積まれた物が全て「宝物」だと認識していることも珍しくありません。まずはその心理を理解することが、対話への第一歩です。
「できなくなった」サインを見逃さないで
親が家をゴミ屋敷にしてしまったことを「怠慢」だと捉えがちですが、実際には加齢により衰えたことで「できなくなった」状態のサインであることを見逃さないようにしましょう。
加齢により身体的な機能が衰えると、体力や筋力の低下、関節の痛みなどにより、掃除やゴミ出しの作業が困難になります。やりたい気持ちはあっても身体が付いていかない状態です。
また、認知症により片付けが困難になるケースもあります。認知症は初期段階でも、もの忘れに加えて集中力や判断力の低下が見られます。ゴミ出しの日を忘れてしまうだけでなく、片付けをしているうちに何をやっていたのかわからなくなってしまう、ゴミの分別がわからない、といった困難に直面している可能性もあるでしょう。
心のSOSがゴミ屋敷として現れることも
身体の機能が老化して失われることもそうですが、高齢に伴いさまざまな喪失が生まれます。身近な友人や配偶者と死別する、退職し社会的役割を失うなどの喪失体験や、社会的に孤立した状態が、精神的な不調や「老年期うつ病」などの疾患につながることがあります。
老年期うつ病では、気分の落ち込みに加えて、疲労感や痛みなどの身体症状も出ることがあり、片付ける気力自体が失われてしまいます。このように心のSOSのサインがゴミ屋敷として現れている場合、必要なのは叱責ではなく医療や福祉のサポートです。
親の心を開く3つのステップ
ゴミ屋敷問題を抱える親との関係作りでは、まず心を開いてもらうことが大切です。ここでは、傾聴・共感・提案の3つのステップでコミュニケーションをとる方法を解説します。言い方一つで関係性も変わってきますので、工夫しながら取り組んでみてください。
ステップ1:『傾聴』まず、親の言い分を否定せずに全て聞く
まずは「片付けて」という言葉を一度封印しましょう。先述した親の心理状態を把握するためにも、良好なコミュニケーション作りから始める必要があります。会話の際には傾聴の姿勢を忘れず、聞き役に徹しましょう。親の言い分を否定せずに全て聞き、途中で遮らずにひとまず受け止めることが重要です。安心して話せる環境で心を開いてくれることで、本当の気持ちがわかることもあるでしょう。会話のきっかけとしては、下記のような声かけを意識してみてください。
- 最近は元気にしていたの?
- 何か困っていることはない?
- 悩んでいることはある?
簡単な声かけをきっかけに話を聞き出しながら、よく眠れているか、生活に変化があったか、身体の具体的な不調はあるか、といった内容を聞き出していくと原因の把握に役立ちます。
ステップ2:『共感』I(アイ)メッセージであなたの心配を伝える
ゴミ屋敷を片付けて欲しいという願いは、伝え方次第で相手の受け取り方が変わってきます。ポイントは主語の違いです。「相手(You)」を主語にして「(あなたは)片付けるべきだ」「(あなたが)だらしないからこうなってしまった」と伝えても、命令や批判として伝わってしまうでしょう。代わりに、「自分(I)」を主語にして下記のように言い換えることで、相手に共感を促すことができます。
- (私は)散らかった部屋でケガをしないか心配だよ。
- (私は)お父さんまたはお母さんの健康状態が心配だから清潔な暮らしをして欲しい。
- (私は)この家が火事にならないかいつも不安で仕方ないよ。
このように、主語を自分にしたアイメッセージを上手に使い、愛情や心配が伝わるように言うと共感を得られやすく良好な関係を築くのに役立ちます。
ステップ3:『提案』小さな成功体験で自信を取り戻させる
ゴミ屋敷のように盛大に散らかった部屋を目の前にすれば、誰でも途方に暮れてしまうでしょう。片付けのコツは、全部一度にやろうとせず小さな場所や些細な片付けから始めて、成功体験を積み重ねて自信をつけることです。まずは、ハードルを極限まで下げて、一緒に片付けようという姿勢で提案してみましょう。下記のように言葉選びも工夫してみてください。
- 今日はテーブルの上だけ一緒に整理してみない?
- このスペースにある物だけ、大切な物とそうでない物に分けてみようよ。
- 玄関だけ簡単に掃除してみない?
「捨てる」という言葉をなるべく使わず、ストレスを感じさせない言い方を心掛けましょう。片付け前と後で写真を撮るなど、小さな成功体験を実感させやすくすることで、自信ややる気を取り戻しやすくなります。
「お助けうさぎ」では、ゴミ屋敷の片付けに力をいれております。お電話・LINE・メールでのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
一人で抱え込まないための相談先と、それぞれの役割
親のゴミ屋敷問題を一人で抱え込まないためには、相談先を見つけておくことが役立ちます。まずは身内から相談を進めますが、身内への相談が難しい場合でも公的な相談機関があるため安心してください。ここでは、相談先の候補と相談によって得られること、それぞれの役割について解説します。
まずは身内から
兄弟姉妹がいる場合には、一人で問題を抱えようとせずまずは相談してみましょう。最初に相談しておくと、片付け後のもめ事なども防ぐことができます。また、事前に相談しておくことで計画も立てやすく、スムーズに作業を進めることができるでしょう。
相談する際には、どうやって片付けていくかのプランとあわせて、費用の分担や役割分担も決めておくと役立ちます。連絡をとる係や実際に作業する係など、細かい部分まで話し合っておきましょう。
公的な支援を頼る
ゴミ屋敷の問題は家族だけでは解決が難しい場合があるため、公的な支援を頼ることも視野に入れておきましょう。公的な相談窓口でまず把握しておきたいのが、地域の高齢者の総合相談を承っている「地域包括支援センター」です。
地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが配置されており、介護サービス事業者や医療機関、民生委員などの地域の関係者と連携して相談内容に対応してくれます。些細なことから相談でき、相談自体は無料のためまずは問い合わせてみると良いでしょう。
専門家の力を借りる
ゴミ屋敷の片付けでは、物理的に片付け作業を実行する必要があります。家族や公的機関のサポートと並行して、片付けの実行部隊として活躍してくれる専門業者のサービスもあわせて検討してみてください。
ゴミ屋敷を片付けてくれる専門業者に依頼すると、プロの作業で効率良く、一部屋を数時間程度で片付けてくれるため問題が一気に片付きます。専門業者はいわば最後の砦でもあるでしょう。ゴミ屋敷の状態をリセットして新しい生活を始めるうえでの、強力な助っ人になってくれます。
専門業者への依頼を決めたら
専門業者に依頼することを決めたら、次は業者選びをおこないます。早く決めて片付けてしまいたい気持ちもあるかと思いますが、親と一緒に業者を選ぶことも大切なポイントです。費用負担の問題もありますので、家族間で随時話し合いながら進めていきましょう。家族間での良好なコミュニケーションを意識しながら取り組むことで、スムーズに進めやすくなります。
ポイント1:親を「説得」するのではなく「一緒に選ぶ」スタンスで
ゴミ屋敷の片付けを専門業者に依頼する際には、業者選びの段階から親に相談し、一緒に選ぶスタンスで進めていきましょう。自分の住んでいる家に知らない業者の人が入って勝手に片付けてしまう、という印象があると、不安や抵抗につながります。
「業者に頼むことに決めた」と事後報告をするのではなく、「どの業者が信頼できそうか、一緒にホームページを見てみない?」と提案するのがおすすめです。業者選びから関わってもらうことで、親を意思決定のプロセスに巻き込めるため、納得したうえでの作業につながりやすいでしょう。
ポイント2:費用負担はどうする?事前に家族で話し合っておくべきこと
お金の問題は家族間でしばしばもめ事になりやすい事柄です。ゴミ屋敷の片付けについても、業者に依頼するとある程度まとまった費用がかかるため、事前に家族で話し合っておく必要があります。高齢になると資産管理もだんだんと難しくなるため、この機会に親の資産状況の確認や将来に向けた準備をおこなうのも良いでしょう。
費用を兄弟姉妹間で分担する際には、役割分担の内容もあわせて検討すると役立ちます。払う金額は同じなのに自分だけやることが多いなど、片付けの負担が偏ると不満が出てくることもあるでしょう。実家から自宅の距離なども関係するため、家族間でのルールを作り、話し合ったことは文章などで残しておくと共有しやすいです。
ポイント3:信頼できる業者の見分け方と(お助けうさぎ)の約束
ゴミ屋敷を片付けてくれる専門業者の中には残念ながら悪徳業者もいるため、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。見極めるポイントは複数ありますが、例えば下記のようなポイントを参考にしてみてください。
- 見積もり金額の内容が明瞭で、相場とかけ離れていないか?
- 信頼できる実績があるか?
- 一般廃棄物処理業の許可など、サービス提供に必要な資格を取得しているか?
- こちらの依頼について丁寧に聞く姿勢があるか?
- プライバシーや個人情報への配慮があるか?
お助けうさぎでは、ご本人の尊厳とご家族の想いを第一に作業を進めることをお約束いたします。作業時はプライバシーに最大限配慮いたしますので、近隣に知られたくない悩みがある場合でもご安心ください。貴重品や探し物がある場合にも、徹底的に捜索しながら片付けを進めていきます。
「お助けうさぎ」では、ゴミ屋敷の片付けに力をいれております。お電話・LINE・メールでのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
一人で抱え込まず、あなたのお悩みをお聞かせください
自分の親がゴミ屋敷に住んでいることは、心配や悲しみ、苛立ちなどさまざまな感情やストレスを引き起こしますが、感情的にならず冷静に対処することが大切です。そして、悩みを一人で抱え込まないことも忘れずに気を付けましょう。正しい知識を身に付け、適切なステップを踏めば、必ず道は開けます。親との対話を重ね、周りのサポートにも上手に頼りながら進めて行けば、より良い環境で再スタートできるでしょう。
私たちお助けうさぎもまた、あなたの力になります。最初の一歩が踏み出せないときは、まずは私たちにお悩みをお聞かせください。丁寧にお話をお伺いし、解決に向けた最適なプランをご提案いたします。いつでもお待ちしております。